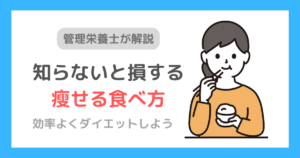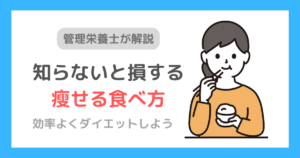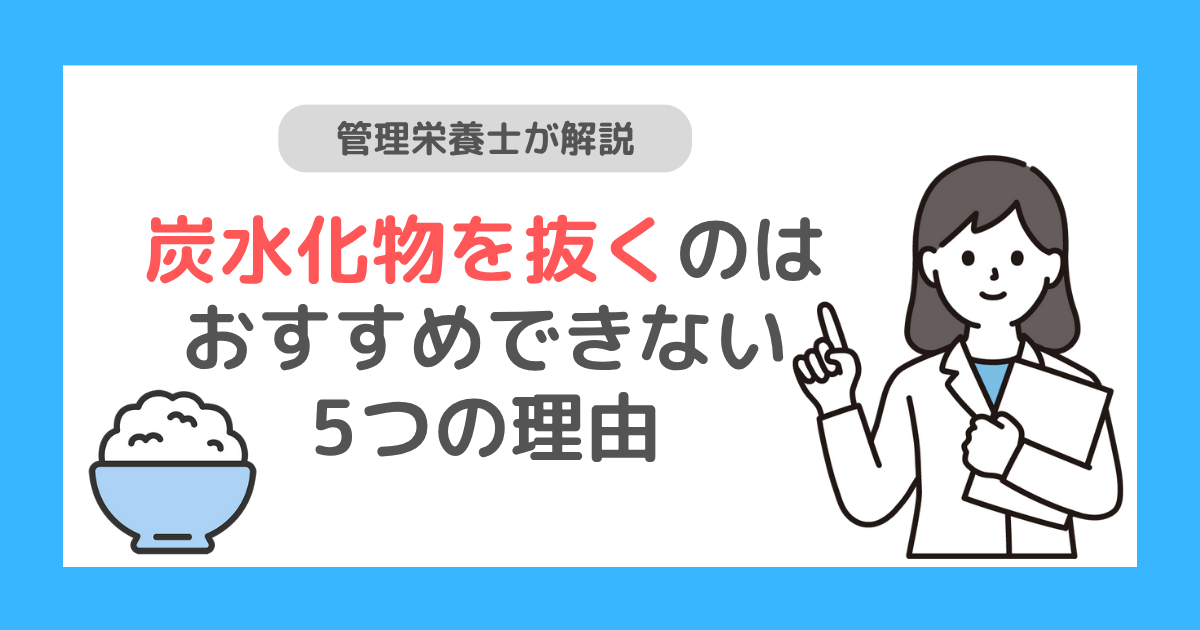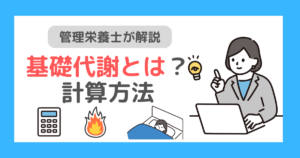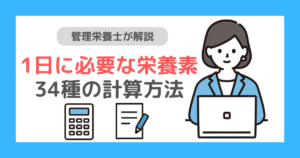- 炭水化物を抜いたら痩せる?
- 健康には影響がないの?
そんな疑問を持っていませんか?
「炭水化物ダイエット」という言葉があるように、炭水化物を抜くと痩せるというイメージを持っている方は多いかもしれません。
実際、ダイエットを始めるときに炭水化物を抜こうとする人は少なくありません。
しかし、管理栄養士の立場から言うと、炭水化物を完全に抜くのはおすすめできません。一時的に体重が減ることはあっても、栄養バランスを崩し、健康に悪影響を及ぼす可能性があるからです。
そこでこの記事では、管理栄養士の視点から、炭水化物を抜くことのリスクと、健康的に痩せるために炭水化物とどう付き合えばよいのかを、栄養学的な観点からわかりやすく解説します。

管理栄養士 こま
- 30代の管理栄養士
- 急性期病院3年・給食委託会社8年
- 病院(2施設)とクリニックで栄養指導経験
- 1日平均4万食提供の委託給食の献立作成を担当
- 関西・関東の病院を中心とした給食提供実績
健康にも気を付けたいと思っている方は、ぜひ最後まで見てください。
炭水化物を抜くのがおすすめできない5つの理由
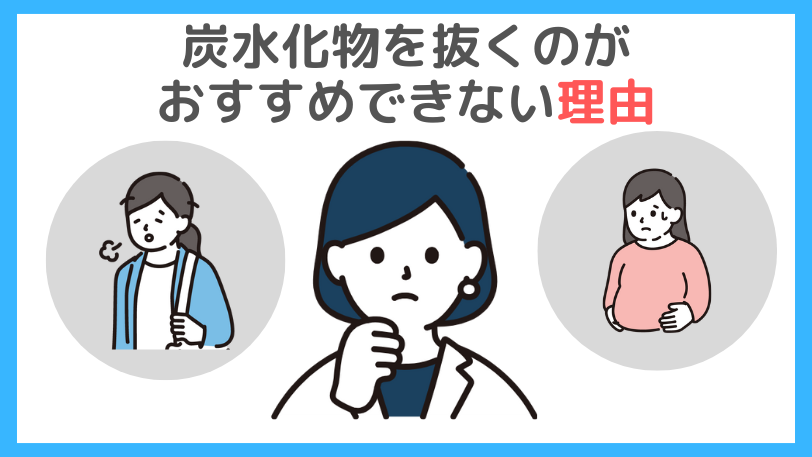
近年では「炭水化物ダイエット」や「糖質制限ダイエット」など、炭水化物を控えるダイエット法が注目されています。
確かに炭水化物の摂取量を減らすことで、減量に繋がることもありますが、管理栄養士の立場から言うと、炭水化物を抜くのはおすすめできません。
その理由はさまざまありますが、特に栄養学的な観点から見たときに、以下のような健康に悪影響を及ぼすリスクがあるからです。
- エネルギー不足となる
- PFCバランスが崩れる
- 筋力低下やたんぱく質不足になる可能性
- 同じ量のカロリーを摂れば結局痩せない
- 体が酸性に傾くリスクがある
エネルギー不足となる
まず、炭水化物を抜くことで身体のエネルギー不足が心配されます。
炭水化物は、三大栄養素(炭水化物・たんぱく質・脂質)の中でも最も効率よくエネルギーに変換される栄養素です。
特に、以下の組織は炭水化物から得られる「ブドウ糖」だけをエネルギー源として利用しています。
- 脳
- 神経組織
- 赤血球
- 腎尿細管
- 精巣
- 酸素不足状態にある骨格筋 など
これらの組織にとって、炭水化物は欠かせないエネルギー源です。
そのため炭水化物が不足すると、疲れやすくなる・集中力が落ちる・頭がぼんやりするといった不調が起こりやすくなります。
PFCバランスが崩れる
炭水化物を抜くと、PFCバランス(エネルギー産生栄養素バランス)が崩れてしまいます。
PFCバランスとは、私たちがエネルギーを得るために必要な「P=たんぱく質」「F=脂質」「C=炭水化物」の摂取比率のことです。
このバランスは、健康的な食生活を送るうえで重要で、長期的には生活習慣病の予防にも関わってきます。
日本人の食事摂取基準(2025年版)では、理想的なPFCバランスは、以下のように設定されています。
- たんぱく質(P):13~20%
- 脂質(F):20~30%
- 炭水化物(C):50~65%
このように、炭水化物は本来、1日のエネルギーの約半分以上を担う重要な栄養素です。
極端に炭水化物を制限すると、PFCバランスが大きく乱れ、結果として生活習慣病のリスクが高まる可能性もあります。健康的に痩せたいと思っている方こそ、炭水化物を適切に取り入れることが大切です。
もっと詳しくPFCバランスとは?
筋力低下やたんぱく質不足になる可能性
炭水化物を抜くと、筋力の低下やたんぱく質不足を招く可能性があります。
 あなた
あなたたんぱく質をしっかり摂っていれば、炭水化物がなくても問題ないのでは?
こう感じる方もいるかもしれません。
しかし、炭水化物には「たんぱく質を節約する」という重要な役割があります。
私たちの体は、まず食事から摂った炭水化物を優先的にエネルギー源として使います。しかし、エネルギーが不足すると、食事から摂ったたんぱく質もエネルギーとして利用されます。
たとえ食事で十分なたんぱく質を摂っていても、炭水化物の不足により、たんぱく質がエネルギー源として使われ、本来の「筋肉や臓器の材料」としての役割を十分に果たせなくなる恐れがあるのです。
また、炭水化物が不足すると、最終的には筋肉のたんぱく質を分解して糖を作り出すようにもなります。これが筋肉量の減少を招き、基礎代謝や体力の低下につながることもあるのです。
つまり、炭水化物をぬくと、結果的にたんぱく質不足のリスクが高まってしまいます。
同じ量のカロリーを摂れば結局痩せない
炭水化物を減らすと、その分のエネルギーをたんぱく質や脂質から補うことになります。
しかし、摂取するカロリーの総量が変わらなければ、体重は減りません。
実際に、日本人の食事摂取基準(2025年版)に以下の記述があります。
炭水化物摂取量の制限によって総エネルギー摂取量を制限すれば減量効果を期待できるが、炭水化物摂取量の制限によって減少させたエネルギー摂取量を他の栄養素(脂質又はたんぱく質)で補い、総エネルギー摂取量が変わらない場合には減量効果は期待できないことを示している。
特に脂質は、1gあたり9kcalと、炭水化物(1gあたり4kcal)の2倍以上のエネルギー量があります。
そのため、炭水化物を減らしたつもりでも、脂質が多くなればかえってカロリー過多になりやすく、減量にはつながらないこともあります。
つまり、「炭水化物を抜けば痩せる」という考えは誤解であり、摂取カロリーが変わらなければ体重も変わりません。



栄養バランスも崩れやすくなるため、健康的な減量にはつながらないのです。
体が酸性に傾くリスクがある
炭水化物を極端に制限すると、体が酸性に傾く可能性があります。
これは、炭水化物が不足した際に、体が脂肪を分解してエネルギーを作る過程で、「ケトン体」という酸性物質が産生されるためです。
通常、ケトン体はある程度であれば問題ありませんが、過剰に産生されると「ケトアシドーシス(代謝性アシドーシス)」という危険な状態になることがあります。
これは体内が強く酸性に傾いた状態で、吐き気、腹痛、倦怠感、呼吸の異常、意識障害などの症状を引き起こすことがあります。
健康な人が軽度の糖質制限を行う程度であれば問題になることは少ないですが、炭水化物を極端に制限する食事法は、体に大きな負担をかけるリスクがあるため注意が必要です。
そのため、炭水化物を完全に抜くような極端な制限はおすすめできません。
炭水化物=太るは誤解


「炭水化物=太る」と思っている方は、意外と多いのではないでしょうか。このようなイメージから、極端に糖質を制限し、主食をまったく食べないという人も少なくありません。
しかし実際には、炭水化物そのものが太る原因ではありません。太る原因は、摂取カロリーが消費カロリーを上回る状態(エネルギー過剰)です。
つまり、炭水化物であっても、量や食べ方によっては太ることもあるし、太らないこともあるということです。
たとえば、
- おにぎり2個(適量)を、バランスのとれた食事の一部として食べる問題なし
- 菓子パン+ジュース+デザートなど、糖質に偏った食事体脂肪として蓄積されやすい
そもそも炭水化物自体のカロリーは高くありません。炭水化物は、1gあたり約4kcal。たんぱく質(1gあたり4kcal)と同じであり、脂質(9kcal)と比べると半分以下。
つまり、炭水化物自体が「太る」わけではありません。
炭水化物を正しく取り入れる2つのコツ


炭水化物を健康的に摂るには、「質」と「量」の両方を意識することが大切です。
質の良い炭水化物を選ぶ
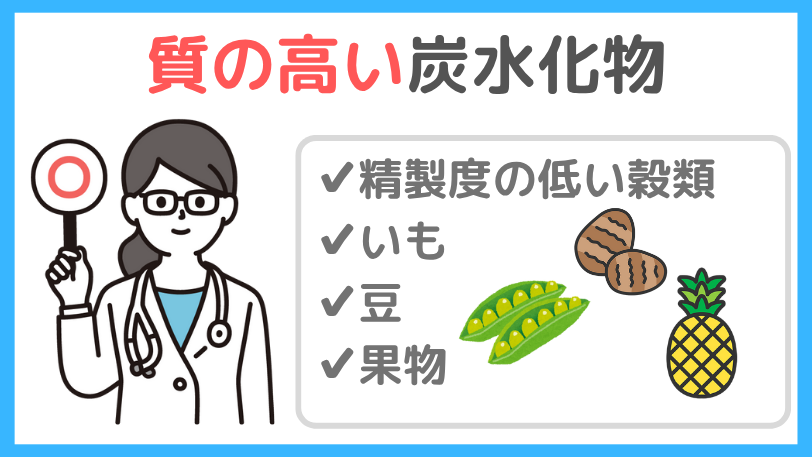
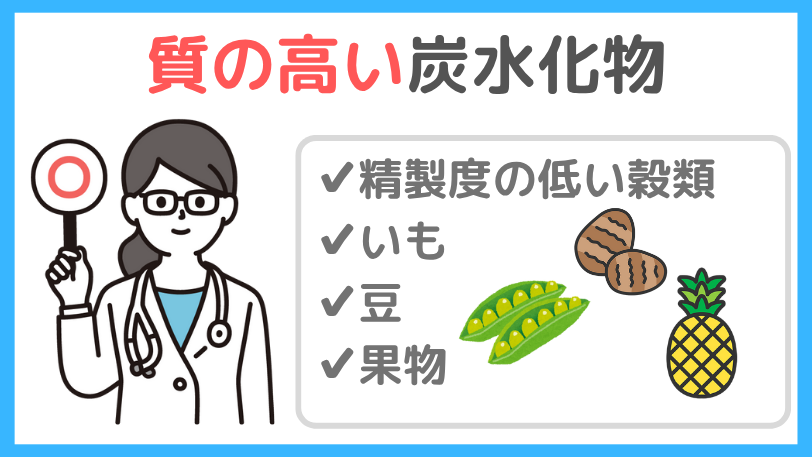
炭水化物には「質の良いもの」と「質の低いもの」があります。
炭水化物の質によって、血糖値の上がり方や栄養価に大きな差が出るため、なるべく食物繊維・ビタミン・ミネラルが豊富な炭水化物を選ぶことが大切です。
以下は、炭水化物の「質」の違いの例です。
| 質の高い炭水化物 | 質の低い炭水化物 |
| ・玄米、胚芽米、発芽玄米、麦飯(押し麦入りご飯)、ライ麦パン、全粒粉パン、オートミール、雑穀米(キヌア、あわ、ひえ など) ・芋類(さつまいも、じゃがいも、里芋、長芋) ・豆類(小豆、黒豆、大豆、レンズ豆、ひよこ豆) ・果物全般 | ・白米、白パン、うどんなど ・甘いお菓子、菓子パン ・砂糖、ブドウ糖果糖液糖 ・清涼飲料水、加糖飲料 ・アルコール類 |
例えば主食で言えば、白米より玄米の方がビタミン・ミネラル・食物繊維が豊富。カロリーはほぼ変わりませんが、栄養価の面では大きな差があります。
「炭水化物=悪いもの」と考えるのではなく、まずは質の良い炭水化物に置き換えることから始めてみましょう。
>>YUWAERUオンラインストア本店
適量を守る
炭水化物は、体にとって大切なエネルギー源ですが、摂りすぎれば、体脂肪として蓄積されやすくなります。



目安として、私が病院食の献立を担当していた時に提供していたご飯量を紹介します。
| 1日のエネルギー量 | ご飯1食分(目安) |
| 1600kcal | 170g |
| 1800kcal | 200g |
| 2000kcal | 220g |
| 2200kcal | 240g |
| 2400kcal | 260g |
※1日のエネルギー量については「1日のカロリー」の記事で分かります。
この量は結構多いと思います。それだけ炭水化物は基礎的なエネルギー源として重要ということです。一方で、これをはるかに超える量を摂ってしまうと、摂りすぎになるので注意してください。
ちなみに、日本人の食事摂取基準(2025年版)では、炭水化物の最低必要量は100g/日と推定されています。これは、ご飯(白米)290gに相当します。



炭水化物を控える場合でも、1食につきご飯お茶碗軽く1杯(約100g)は必ず摂る方が良いでしょう。
バランスの良い食事が基本
減量を考える際にも、まず大切なのはバランスの取れた食事です。
具体的には、以下のような食品がそれぞれに該当します。
- 主食:ご飯、パン、麺など
- 主菜:肉、魚、卵、大豆製品など
- 副菜:野菜、いも類、海藻、きのこなど
これらの食品を一つに偏ることなく、適切な量を摂ることが大切です。炭水化物を極端に減らすことは避け、減量中でも毎食この3つがそろうように意識しましょう。
バランスの良い食事のまま、全体量の調整や、主食や主菜をやや控えめに。その分副菜を増やしてかさましするなどが健康的な減量方法です。
家族の栄養バランスが心配な方へ
おいしさで人気のオイシックスなら
買い出しなしで健康的な夕食に!


\ 初めての方限定!税込2980円! /
※定期購入ではなく、1回限りのセット
よくある質問(Q&A)


炭水化物を抜くとすぐに体重が減るのはなぜ?
炭水化物を控えると、体内の糖質(グリコーゲン)と一緒に水分が減るため、最初の数日で体重が大きく落ちることがあります。
ただし、これは脂肪が減ったわけではなく、一時的な水分減少によるものです。長期的には、極端な制限はリバウンドや健康リスクを招く恐れがあります。
炭水化物を抜くと痩せるの?
一時的には体重が減ることがありますが、筋肉量の減少や代謝の低下を招き、結果的に痩せにくい体質になる可能性もあります。
また、極端な糖質制限は栄養バランスが崩れやすく、健康的な減量とは言えません。
じゃあ、炭水化物はどれくらい摂ればいいの?
目安としては、1食にご飯で言えば100~150g程度(軽く1膳)(活動量や体格によって変動あり)。
大切なのは「抜く」のではなく、量や質(白米→玄米、全粒粉など)を見直すことです。
夜は炭水化物を食べない方がいい?
夜に食べ過ぎると脂肪になりやすいのは確かですが、完全に抜く必要はありません。
特に夕食の時間が早い、または寝る前まで時間がある場合は、少量の炭水化物を摂った方が安眠や筋肉維持に良いこともあります。
炭水化物を抜いたら頭がぼーっとするのはなぜ?
脳は炭水化物から得られるブドウ糖をエネルギーにしているからです。極端に炭水化物を制限すると、集中力の低下や疲労感、イライラなどの症状が出ることがあります。
パフォーマンスを保つためにも、適量の炭水化物は必要不可欠です。
炭水化物を食べながらでも痩せられる?
はい、十分可能です。主食・主菜・副菜をそろえたバランスの良い食事を基本にし、全体のエネルギー摂取量を調整することで健康的に痩せられます。
炭水化物を適度に取り入れることで、代謝を保ち、リバウンドしにくい減量ができます。
まとめ|炭水化物は抜くのではなく「選ぶ・調整する」が正解!


この記事では、炭水化物を抜くことのリスクと、健康的に痩せるために炭水化物とどう付き合えばよいのかを、栄養学的な観点から解説しました。
要点をまとめると以下の通り。
- 炭水化物を極端に抜くと健康リスクが高まるのでおすすめしない
- 炭水化物=太るは誤解
- 大切なのは質の良い炭水化物を適量取り入れること
- 減量中でも主食・主菜・副菜がそろったバランスの良い食事が基本
世の中には「炭水化物を抜けば痩せる」という誤った情報が多く出回っていますが、管理栄養士の立場から言えば、炭水化物を完全に抜くダイエットは推奨できません。
炭水化物を適切に取り入れながらでも、無理なく・健康的に体重を落とすことは可能です。
リバウンドしにくく、体への負担も少ない方法で、長く続けられる食生活を目指しましょう。



この機会に、毎日の食事を見直し、「バランスの良い食事」を意識するきっかけになれば幸いです。
今なら人気のOisixCookBoxが税込2980円でお得に試せるチャンスです!


\ 初めての方限定!1食298円! /
※定期購入ではなく、1回限りのセット