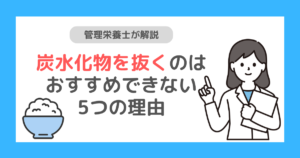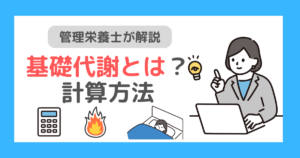- 五大栄養素って具体的に何があるの?
- それぞれの役割って?
- 毎日の食事にどう取り入れればいいの?
こういった疑問を抱えていませんか?
五大栄養素とは、健康を維持するために欠かせない以下の5つの栄養素のことを指します。
- 炭水化物(糖質)
- 脂質
- たんぱく質
- ビタミン
- ミネラル
これらはすべて、私たちの体を動かし、つくり、整えるために不可欠な存在です。しかし、現代の食生活では、偏った食事や誤った情報などにより、五大栄養素が不足しがちな人も多いです。
栄養バランスが崩れることで、気づかないうちに体調不良や生活習慣病のリスクを高めている可能性もあります。
そこでこの記事では、管理栄養士の視点から、五大栄養素の基礎、日々の食生活への取り入れ方まで分かりやすく解説します。

管理栄養士 こま
- 30代の管理栄養士
- 急性期病院3年・給食委託会社8年
- 病院(2施設)とクリニックで栄養指導経験
- 1日平均4万食提供の委託給食の献立作成を担当
- 関西・関東の病院を中心とした給食提供実績
「自分や家族の食生活を健康にしたい」と考えている人はぜひ最後まで読んでください。
五大栄養素とは欠かせない基本的な栄養素

五大栄養素とは私たちが健康を維持し、生きていくうえで欠かせない基本的な栄養素のことです。具体的には、以下の5つの栄養素のことを指します。
- 炭水化物(糖質)
- 脂質
- たんぱく質
- ビタミン
- ミネラル
そのうち、炭水化物、脂質、たんぱく質は「エネルギー産生栄養素」や「三大栄養素」とも呼ばれ、体内でエネルギーを生み出すことができる栄養素です。
それぞれのエネルギー量は次の通り。
- 炭水化物(糖質)・・・4kcal/g
- 脂質・・・9kcal/g
- たんぱく質・・・4kcal/g
詳しくはこちら【三大栄養素とは】
ビタミンとミネラルはエネルギーそのものにはなりませんが、代謝を助けたり、身体の機能や構造を支える重要な役割を担っています。
五大栄養素の役割と特徴
五大栄養素は、それぞれ体にとって異なる重要な役割を持っています。
炭水化物は効率的なエネルギー源

炭水化物は、私たちの体にとって最も効率的なエネルギー源です。
体内に取り込まれると、炭水化物は消化されて最小単位のブドウ糖に分解されます。ブドウ糖は細胞の主要なエネルギー源として利用され、特に以下のような部位はブドウ糖以外のエネルギーを使うことができません。
- 脳
- 神経組織
- 赤血球
- 腎臓の尿細管
- 精巣
- 酸素不足の骨格筋
このため、炭水化物は体のエネルギー供給において非常に重要な役割を果たしています。
炭水化物は大きく分けて「糖質」と「食物繊維」から成り立っています。
炭水化物 = 糖質 + 食物繊維
糖質:体内で消化・吸収され、エネルギー源となる
食物繊維:消化されにくく、エネルギー源にはなりにくい
食物繊維はほとんど消化されませんが、以下のような健康効果があります。
- 腸内環境を整える
- 血糖値の上昇を緩やかにする
そのため、同じ「炭水化物」でも、糖質と食物繊維の割合によって体への影響が異なります。
糖質が多い食品はエネルギー源として利用されやすく、食物繊維が豊富な食品は健康維持や生活習慣病の予防に役立ちます。
ご飯・パン・麺類・いも
もっと詳しくはこちら【炭水化物とは】
脂質はエネルギーの貯蔵
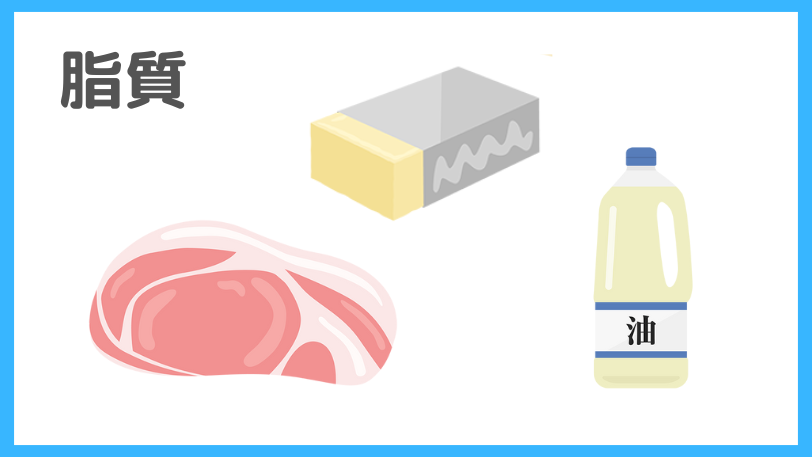
脂質は、体内でエネルギーを効率よく貯蔵する役割のほか、細胞膜やホルモンの材料としても欠かせない栄養素です。
炭水化物やたんぱく質が1gあたり約4kcalのエネルギーを持つのに対し、脂質は1gあたり約9kcalと、約2倍以上のエネルギーを供給します。そのため、体は効率よくエネルギーを蓄えるために脂質を優先的に貯蔵します。
しかし、脂質を過剰に摂取するとエネルギー過多となり、肥満や生活習慣病のリスクが高まるため注意が必要です。
脂質は、構成する脂肪酸の種類によって、体に良い油とそうでない油があります。
| 積極的に摂りたい油 | 控えたい油 |
| 魚の油、ごま油、アマニ油など | バター、ラード、マーガリン、ショートニングなど |
健康的な脂質の摂取を心がけることが、生活習慣病予防にもつながります。
詳しい脂肪酸の種類など、もっと詳しくはこちら脂質とは?
たんぱく質は体の構成成分
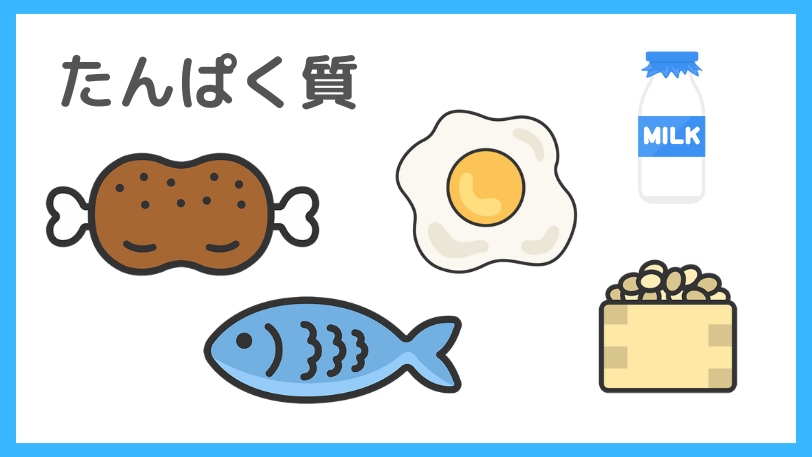
たんぱく質は、エネルギー源にもなりますが、主な役割は体の構成と機能のサポートにあります。
筋肉や臓器をはじめ、酵素やホルモン、免疫抗体など、体のさまざまな重要な成分を作り出しています。
体内に入ったたんぱく質は、アミノ酸に分解されます。アミノ酸は体の組織修復や新陳代謝に使われ、健康な体を維持するうえで欠かせません。
質の良いたんぱく質は体に効率よく利用されやすいです。
肉・魚・卵・大豆製品・牛乳・乳製品
これらの食品は良質なたんぱく質を豊富に含んでいるため、日々の食事ではメインのおかず(牛乳・乳製品は除く)として取り入れることが推奨されています。
具体的なアミノ酸など、もっと詳しくはこちらたんぱく質とは?
ビタミンは代謝を助ける

ビタミンは、身体機能を正常に保つために欠かせない栄養素です。
多くのビタミンは、体内で働く酵素をサポートする「補酵素」として機能し、代謝や免疫、細胞の再生など、さまざまな生命活動を支えています。
体内ではほとんど合成することができないため、基本的に食事から摂取する必要があります。
ビタミンは全部で13種類あり、「水溶性ビタミン」、「脂溶性ビタミン」の2つのグループに分かれています。
| 水溶性ビタミン | 脂溶性ビタミン |
| VB1、VB2、ナイアシン、VB6、VB12、葉酸、パントテン酸、ビオチン、VC | VA、VD、VE、VK |
水溶性ビタミンは、水に溶けやすく、余分に摂取した分は量に排出されるため、毎日こまめに摂る必要があります。
脂溶性ビタミンは油に溶けやすい性質があり、脂肪組織や肝臓に蓄えられます。摂りすぎると過剰症を起こすこともあります。
雑穀類、肉類、魚介類、野菜、きのこ、いも類、海藻類、種実類、果物
特定の食品に偏ることなく、いろいろな種類をバランスよく食べることが、ビタミン不足を防ぐカギです。
それぞれビタミンの多い食材はこちらの記事で確認できますビタミンとは?
ミネラルは体の生理作用の調整

ミネラルは、骨や歯の形成、神経や筋肉の働き、体内の水分バランスや酸塩基平衡の調整など、身体のさまざまな生理機能を支える欠かせない栄養素です。
体内では合成できないため、すべて食事から摂取する必要があります。必要な量はごくわずかでも、健康維持に重要な役割を果たします。
ミネラルは多くの種類がありますが、摂取基準が設けられているのは13種類で、「多量ミネラル」と「微量ミネラル」の2つに分けられます。
| 多量ミネラル | 微量ミネラル |
| ナトリウム、カリウム、カルシウム、マグネシウム、リン | 鉄、亜鉛、銅、マンガン、ヨウ素、セレン、クロム、モリブデン |
ナトリウムは過剰に摂取しやすく、高血圧など生活習慣病のリスクにつながるため、摂りすぎに注意が必要です。
雑穀類、肉類、魚介類、野菜、きのこ、いも類、海藻類、種実類、果物
ミネラルは微量でも大きな働きをする栄養素です。バランスの取れた食生活を心がけることが、ミネラル不足・過剰の予防につながります。
それぞれミネラルの多い食材はこちらの記事で確認できますミネラルとは?
第6・7の栄養素とは?

五大栄養素は栄養の基本としてよく知られていますが、近年ではこれに加えて「第6の栄養素」や「第7の栄養素」と呼ばれる成分も注目されています。
第6の栄養素:食物繊維
食物繊維は炭水化物の一種で、人間の消化酵素では消化されない成分です。
以下のようなさまざまな生理作用があることから、「第6の栄養素」として注目されています。
- 腸内環境の改善
- 大腸がんの予防
- 血糖値の上昇を緩やかにする
近年の日本人は野菜の摂取量が不足しており、食物繊維の摂取量も不足しがちです。
健康的な食生活を送るためには、意識して食物繊維を摂ることが大切です。
雑穀類、野菜、きのこ、芋類、海藻類、種実類、果物
1日に摂るべき食物繊維の目安量は成人で20g以上とされています。まずは毎食の中に野菜+もう1品(海藻やきのこなど)を加えるのがオススメです。
詳しくはこちら【食物繊維とは】
第7の栄養素:ファイトケミカル
ファイトケミカルとは、野菜、果物、穀類などの植物性食品の色素、香、アクなどの成分から発見された物質です。代表的なものにカロテノイドやポリフェノールなどがあります。
これらは以下のような体に有益な作用があることから、「第7の栄養素」として注目されています
- 感染予防
- 抗酸化作用
- がんの予防
代表的なファイトケミカルの例は以下の通り。
| 種類 | 食品の例 | 機能 |
| β-カロテン | にんじん・かぼちゃ | 抗酸化作用・動脈硬化予防 |
| リコピン | トマト | |
| フラボノイド | 玉ねぎ | 抗酸化作用・高血圧予防 |
| ルテイン | とうもろこし | 抗酸化作用 |
| アントシアニン | なす・赤しそ | 抗酸化作用・加齢による視力低下 |
| イソチオシアネート | 大根・キャベツ | 抗酸化作用・抗ピロリ菌 |
ファイトケミカルは「色」や「香り」が強い野菜・果物に多く含まれています。いろいろな色の野菜をバランスよく食べることが、健康への近道です。
五大栄養素をバランスよく摂るコツ

五大栄養素を理想的なバランスで摂るにはどうしたらいいのでしょうか?
「栄養素の割合を細かく考えながら食事をするのは難しい…」と感じるかもしれませんが、心配はいりません。
食の基本である「主食・主菜・副菜」をバランスよく組み合わせれば、自然と五大栄養素をバランス良く摂ることができます。
主食はご飯から摂る
主食にはご飯、パン、麺などがありますが、特にご飯を主食にすることを意識しましょう。日本食がバランスの良い食事とされる理由の一つに、主食がご飯であることが挙げられます。
そのため、1日に2食以上はご飯を主食にした食事を心がけるのがおすすめです。適量は、ご飯1〜2杯程度が目安です。
 管理栄養士 こま
管理栄養士 こま多すぎても少なすぎてもバランスが崩れてしまうため、適量を意識して摂ることが大切です。
必要カロリーに対するご飯量など、もっと詳しくはこちら主食とは
主菜は良質なたんぱく質を適量
主菜は、肉類・魚類・卵類・大豆製品の良質なたんぱく質食材を使った料理から摂りましょう。
主菜の具体的な量やポイントは以下の通り。
- 肉魚の1回の適量は60~120g程度
- 肉は赤身肉を選ぶ
- 魚は週に4回以上を目指す
- 卵は1日1~2個までを目安に
- 大豆製品は1日50~100gを積極的に



質と量を意識して、さまざまな食材を取り入れるのがポイントです。
調理方法のコツなど、もっと詳しくはこちら主菜とは
副菜は特に不足しないよう注意
副菜には、野菜・いも類・きのこ・海藻などを使った料理が含まれます。
これらは栄養バランスを整えるうえで非常に大切ですが、日常の食事では不足しやすい部分でもあります。だからこそ、意識して積極的に摂ることが大切です。
- 副菜の具体的な量やポイントは以下の通り。
- 野菜は1日350g(緑黄色野菜120g)
- いもは1日50g程度
- 海藻は1日3g程度
- きのこは1日20~30g程度
十分な副菜を摂るには、1日5皿程度の副菜が必要とされています。



できるだけ多くの食材を使用し、しっかりと量を確保しましょう。
副菜の上手な摂り方など、もっと詳しくはこちら副菜とは
- 炭水化物は、食物繊維が豊富な全粒穀物も取り入れる
- たんぱく質は、肉や魚、大豆製品、乳製品をバランスよく摂取する
- 脂質は、魚の油や植物油など良質な脂質を中心にし、バターや加工油脂は控えめにする
- 果物、牛乳・乳製品もプラスしよう
まとめ:五大栄養素を知って、日々の食生活を見直そう


この記事では、五大栄養素の基礎知識や摂り方について解説しました。
要点をまとめると以下の通り。
- 五大栄養素は「炭水化物」「脂質」「たんぱく質」「ミネラル」「ビタミン」
- 「炭水化物」「脂質」「たんぱく質」は主にエネルギー源になる
- 「ミネラル」「ビタミン」は身体の機能を調整する重要な栄養素
- 近年は「第6の栄養素」として食物繊維、「第7の栄養素」としてファイトケミカルの重要性も注目されている
- すべての栄養素をバランスよく摂取するには、主食・主菜・副菜をそろえた食事が基本
五大栄養素は、私たちの体をつくり、動かし、守るための土台となる栄養素です。
どれか一つでも不足すると、体調や健康に影響を及ぼす可能性があります。
健康な毎日を送るためには、どの栄養素もバランスよく摂ることが大切です。
まずは、日々の食事を見直し、無理なく続けられるバランスの良い食生活を意識していきましょう。



まずは、主食・主菜・副菜を組み合わせた食事を意識しよう




参考文献(2025年6月25日参照)
- 日本人の食事摂取基準(2025年版)|厚生労働省
- 公益社団法人日本栄養士会(2024)『ヘルシーダイアリー2024』