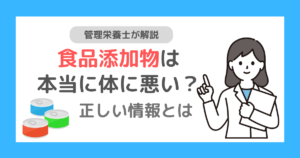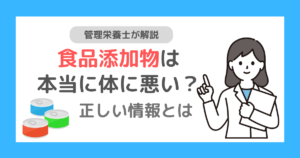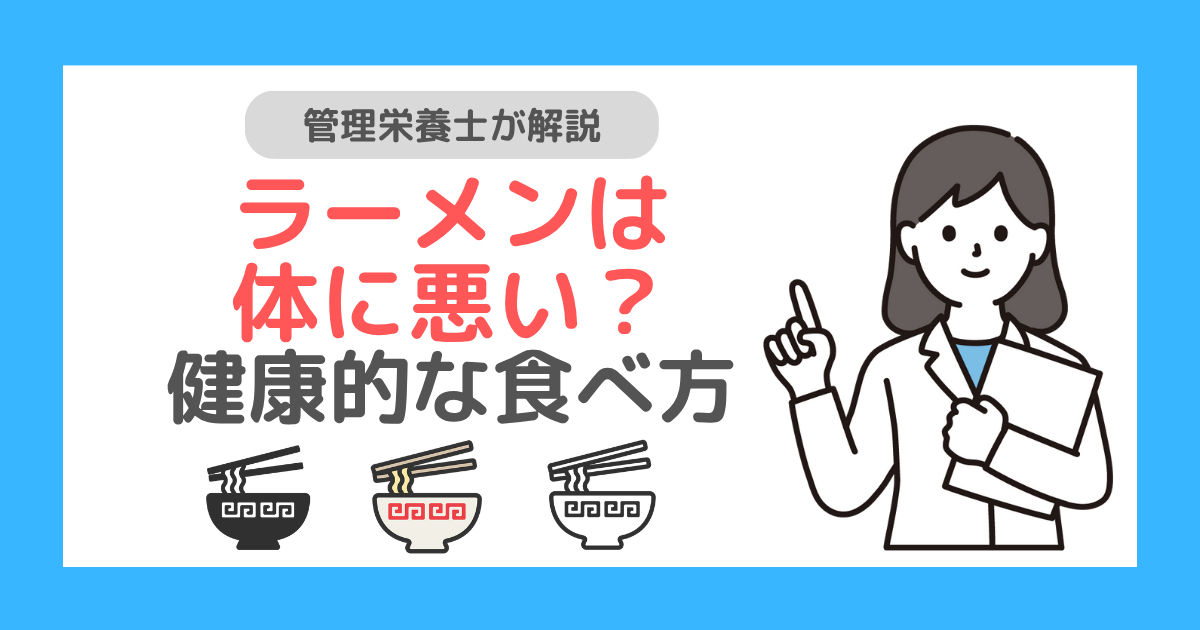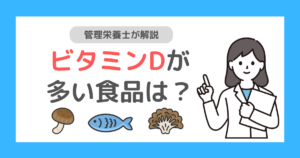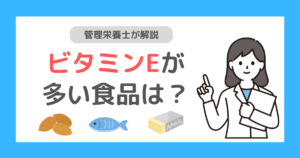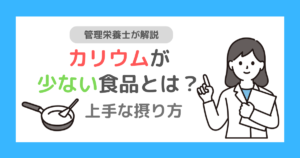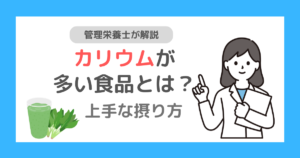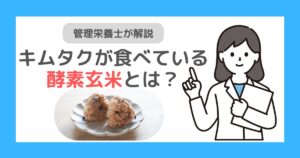- ラーメンって体に悪いの?
- 健康的に食べる方法はある?
そんな疑問を感じたことはありませんか?
みんな大好きなラーメン。もちろん私も大好物です。でも、「ラーメンは体に悪い」「控えたほうがいい」といった声を聞くと、ちょっと気になってしまいますよね。
でも、ポイントを押さえれば、ラーメンを楽しみながら健康も守ることは可能です。
この記事では、管理栄養士の視点から「ラーメンが体に悪い」と言われる理由と、健康的に食べるための工夫やコツをわかりやすく解説します。

管理栄養士 こま
- 30代の管理栄養士
- 急性期病院3年・給食委託会社8年
- 病院(2施設)とクリニックで栄養指導経験
- 1日平均4万食提供の委託給食の献立作成を担当
- 関西・関東の病院を中心とした給食提供実績
ラーメンが大好き!だけど健康面も気になる…という方は、ぜひ最後まで見てください。
ラーメンは本当に体に悪いのか?

「ラーメンは体に悪い」といったイメージを持っている方も多いのではないでしょうか。
では、実際のところはどうなのでしょうか?
管理栄養士としての私の見解では、ラーメンを食べたからといって、すぐに健康に悪影響が出るわけではありません。
ラーメンのどこに注意すべきなのか、そして健康的に楽しむためにはどう付き合っていけばよいのか、正しい知識を持っておくことが大切です。
ラーメンが体に悪いと言われる理由

ラーメンが体に悪いと言われる理由は、大きく分けて以下の3つです。
- 塩分の摂りすぎにつながる
- 栄養バランスが偏りやすい
- 噛まずに食べやすく、早食いになりやすい
塩分の摂りすぎにつながる
ラーメンが体に悪いと言われる大きな理由のひとつが、塩分の多さです。
日本人の食事摂取基準(2025年版)では、1日の塩分摂取の目安は以下の通りとされています。
- 成人男性:7.5g未満
- 成人女性:6.5g未満
しかし、ラーメン1杯(特にスープまで飲み干した場合)で、この目安を簡単に超えてしまうことがあります。
ラーメンの種類やお店にもよりますが、塩分量が1杯で10g以上になるケースも珍しくありません。
もともと日本人は、塩分の多い食文化の中で暮らしており、日常的に塩分摂取量が高めです。そのため、ラーメンを頻繁に食べると、長期的に塩分摂取量が過多になり、健康を害してしまう可能性があるのです。
栄養バランスが偏りやすい
ラーメンが体に悪いと言われる理由のひとつに、栄養バランスが偏りやすいことが挙げられます。
ラーメンを食べるときは、チャーハンをセットにしたり、替え玉を追加したりと、炭水化物に偏りやすい傾向があります。さらに、チャーシューや脂の多いスープによって、脂質の摂取量も多くなりがちです。
一方で、野菜は少なく、たんぱく質や食物繊維、ビタミン・ミネラルなどが不足しやすいという問題があります。
実際に私も、病院で献立作成をしていた際、ラーメンをメインにした献立は栄養バランスを取るのが非常に難しく、苦労した経験があります。
専門的に栄養価を計算してもバランスを取るのが難しいため、何も考えずに“好きなように”ラーメンを食べていると、栄養が大きく偏ってしまうリスクが高くなります。
これを頻繁に繰り返すと、慢性的な栄養の偏りにつながり、太りやすくなったり、ビタミン・ミネラル・食物繊維の不足による体調不良や生活習慣病のリスクが高まる可能性もあるのです。
噛まずに食べやすく、早食いになりやすい
ラーメンが体に悪いと言われる理由のひとつに、噛まずに食べてしまいやすいという点があります。
ラーメンに限らず、うどんやそばなどの麺類は、すすって食べる習慣があるため、自然と噛む回数が少なくなりがちです。噛む回数が少ないと、消化が悪くなるだけでなく、満腹感を感じにくくなるため、つい食べすぎてしまう原因にもなります。
さらに、ラーメンと一緒に食べることが多いのは、チャーハンや餃子など、糖質・脂質が多いメニュー。早食いのまま満腹中枢が刺激される前にこれらを食べてしまうと、必要以上にカロリーを摂取してしまうことも少なくありません。
また、早食いは血糖値の急上昇を引き起こしやすく、体に負担がかかったり、脂肪がつきやすくなったりすることもあります。
 管理栄養士 こま
管理栄養士 こまこれらの理由からラーメンは体に良くないと言われることが多いです。
ラーメンをよく食べる人の健康リスク


では、ラーメンをよく食べる人には、どのような健康リスクがあるのでしょうか?
実は、ラーメンを長期間にわたって頻繁に食べていると、生活習慣病のリスクが高まり、体に悪影響を及ぼす可能性があります。
塩分の摂りすぎによる影響
ラーメンを頻繁に食べる人は、塩分の摂りすぎに繋がっている可能性があります。
塩分を摂りすぎると、以下のようなリスクが高まります。
- 血圧が上がる
- 心臓への負担が増える
- 腎臓に負担がかかる
塩分には水分を体内に引き込む作用があり、摂りすぎると血液量が増えて血管に圧力がかかり、高血圧の原因になります。
高血圧になると、心臓や腎臓など血管が密集している臓器に負担がかかりやすく、長期間続くことで機能が低下し、将来的な病気につながるリスクも考えられます。
栄養バランスの偏りによる影響
ラーメンばかり食べていると、どうしても炭水化物と脂質に偏った食生活になりがちです。
その結果、次のような影響が出る可能性があります。
- 肥満・脂質異常症
- 食物繊維不足による便秘
- ビタミン・ミネラル不足による免疫力の低下や疲れやすさ
栄養バランスが崩れた食生活が続くと体の調子を整える栄養素が不足し、疲れやすくなったり、風邪をひきやすくなるといった不調につながることもあります。
長期的に見ると、生活習慣病のリスクを高めてしまう可能性があるのです。
健康的にラーメンを食べるコツ


「ラーメン=体に悪い」というイメージがありますが、食べ方を少し工夫するだけで、健康的に楽しむことができます。
ここでは、誰でもすぐに実践できるラーメンの食べ方のコツをご紹介します。
- スープは3口までを目安に
- 野菜が多いラーメンを選ぶ
- たんぱく質源も意識してとる
- 「炭水化物+炭水化物」の組み合わせは控える
- 野菜から先に食べる
- よく噛んで、ゆっくり食べる
- 食べる頻度は週に1回を目安に
スープは3口までを目安に


管理栄養士として一番推奨したいのが、ラーメンのスープは「3口まで」にとどめることです。
ラーメンのスープはとても美味しく、つい全部飲み干してしまいたくなるかもしれません。しかし、スープには大量の塩分が含まれており、過剰に摂取すると健康に悪影響を及ぼします。
ラーメンは麺にも塩分が含まれているため、スープを残したとしても塩分の摂りすぎになることがあります。そこにスープを加えてしまうと、さらに塩分過多に。体への負担が大きくなってしまいます。
健康のためにも、スープはなるべく残し、「飲んでも3口まで」を意識するようにしましょう。
野菜が多いラーメンを選ぶ


ラーメンを食べるときに特に不足しがちなのが「野菜」です。一般的なラーメンに入っている野菜といえば、もやしやねぎが少しだけ。健康的な食事は、1食あたり野菜を120g以上は摂るのが理想とされており、普通のラーメンではどうしても足りません。
そんな中でおすすめしたいのが、最初から野菜がたっぷり入ったラーメンを選ぶこと。たとえば、「ちゃんぽん」や「野菜ラーメン」などは、野菜の量がしっかりしていて栄養バランスも比較的整っています。
また、お店によって野菜の量には差があるため、できるだけ「野菜多め」のラーメンを提供しているお店を選ぶのもポイントです。
さらに、野菜があまり入っていない場合でも、トッピングを工夫することで野菜をプラスすることができます。
ねぎ、もやし、キャベツ、ほうれん草、メンマ、玉ねぎ、ニラなどの野菜系トッピングが用意されている場合は、ぜひ積極的に追加してみましょう。
たんぱく質源も意識してとる
ラーメンは炭水化物が中心になりやすく、たんぱく質が不足しがちです。健康的な食事を意識するなら、たんぱく質もきちんと摂るよう心がけましょう。
たんぱく質源としてよく使われるのがチャーシューですが、種類によって脂の量がかなり違います。脂身が多いチャーシューは、たんぱく質より脂質の割合が高くなる傾向があるため、できれば脂の少ない部位を使ったチャーシューを選ぶのがおすすめです。
また、煮卵やゆで卵をトッピングするのも良いたんぱく質補給になります。1個加えるだけでも栄養バランスが良くなるので、積極的に活用してみてください。
「炭水化物+炭水化物」の組み合わせは控える
ラーメンを食べるとき、ついごはんやチャーハンと一緒に頼んでしまうことはありませんか? いわゆる「炭水化物+炭水化物」の組み合わせです。
このような食事は、エネルギーの摂取量が過剰になったり、血糖値が急上昇しやすくなるなど、健康面でのリスクが高まります。
ラーメンはそれ自体が主食です。できるだけごはんやチャーハンは組み合わせず、ラーメン単体で満足できるように意識しましょう。
どうしてもラーメンだけでは物足りない場合は、唐揚げやサラダなど、たんぱく質源や野菜をプラスするのがおすすめです。栄養バランスが整い、満足感も得やすくなります。
また、「替え玉」にも要注意。麺を追加することで炭水化物の摂取量がさらに増えるため、必要以上に頼まないように気をつけましょう。
野菜から先に食べる
ラーメンを食べるとき、つい最初に麺からすすってしまいがちですが、健康を意識するなら「野菜から先に食べる」ことをおすすめします。
ラーメンは主に炭水化物でできているため、最初に麺を食べると血糖値が急激に上昇しやすく、体への負担が大きくなる可能性があります。
その点、野菜には食物繊維が豊富に含まれており、最初に食べることで血糖値の上昇をゆるやかにする効果が期待できます。
理想的な食べる順番は、
野菜 → たんぱく質(チャーシューや卵など) → 麺。
このように少し順番を工夫するだけでも、血糖値のコントロールや満腹感の持続につながり、健康面でのメリットがあります。
ぜひ、次にラーメンを食べるときは「食べる順番」にも注目してみてください。
よく噛んで、ゆっくり食べる
ラーメンを食べるときは、よく噛んでゆっくり味わうことも大切なポイントです。
麺類はどうしてもすすって食べることが多く、噛む回数が少なくなりがち。その結果、食べるスピードが早くなり、満腹感を感じる前に食べ過ぎてしまうことがあります。
早食いを防ぐためにも、意識して一口ごとにしっかり噛むことが大切です。噛む回数を増やすことで、消化が良くなり、満足感も得やすくなります。
食べる頻度は週に1回を目安に
ここまでラーメンを健康的に食べる工夫を紹介してきましたが、「やっぱり好きなように食べたい!」と感じる方も多いと思います。そうした気持ちはもちろん自然なことですし、無理に我慢しすぎると逆にストレスになることもあります。
そこでおすすめしたいのが、食べ方を厳しく変えるのではなく、「食べる頻度」を見直すことです。たとえ従来通りの食べ方でも、頻度を減らせば、ラーメンによる健康への影響はぐっと少なくなります。
目安としては、週に1回程度に抑えるのが理想的。できれば、ラーメンに限らず、麺類全体で週1回までを目標にすると、より効果的です。



実際に、病院の献立などでも、麺類は週1回になっていることが多かったです。
逆に言えば、週に1回はラーメンを楽しんでOKということです。頻度を調整するだけで、無理なく健康リスクを減らすことができるので、ぜひ自分なりのペースで取り入れてみてください。
ラーメンを食べた後にできること


ラーメンを食べるときだけでなく、食べた後にも健康のために意識できることがあります。
「食べてしまったからもう仕方ない」と思わずに、食後のちょっとした行動で体への負担を軽くすることができます。
以下のポイントを参考に取り入れてみてください。
水分を補給する
ラーメンを食べたあとは、塩分を多く摂取している場合がほとんどです。体内の余分な塩分を排出するためにも、水分補給を心がけましょう。
甘い清涼飲料水やスポーツドリンクは、糖分や塩分をさらに摂ってしまう可能性があるため、避けたほうが良いです。



ラーメンの後は、意識してコップ1〜2杯の水分を摂ろう!
次の食事で調整する
ラーメンを食べたあとは、次の食事で栄養バランスを整えることが大切です。
たとえば、たんぱく質や野菜が不足していた場合は、次の食事で意識的に多めに摂るようにしましょう。逆に、塩分や脂質を多く摂りすぎたと感じたら、次の食事は油を控えめにし、味付けも薄めのものを選ぶのがおすすめです。
食事の前後でバランスをとることを意識するだけで、健康への影響を和らげることができます。ぜひ実践してみてください。
運動やウォーキングを取り入れる
ラーメンを食べてから1〜2時間後に、軽い運動を取り入れるのがおすすめです。散歩やストレッチなどの軽い運動は、血糖値の急上昇を抑える効果が期待できます。
「少し食べ過ぎたかも」と感じたときは、たった10分のウォーキングでも十分効果的です。無理なくできる運動を取り入れましょう。
まとめ|ラーメンは「食べ方」で健康リスクを下げられる


この記事では、ラーメンが体に悪いと言われる理由、健康的に食べるための工夫やコツを解説しました。
要点をまとめると以下の通り。
- ラーメンは食べる頻度や食べ方によって、健康リスクが高まることがある
- 塩分の過剰摂取や栄養バランスの偏り、噛む回数の減少がリスク要因に
- 頻繁に食べると生活習慣病のリスクが高まる可能性がある
- 健康的にラーメンを食べるポイント
┗ スープは3口までに抑える
┗ 野菜が多いラーメンを選ぶ
┗ たんぱく質もきちんと摂る
┗ 炭水化物に偏らないようにする
┗ 野菜から先に食べる
┗ よく噛んでゆっくり食べる
┗ 食べる頻度は週1回までにする
ラーメンは多くの人に愛される美味しい食べ物ですが、健康面が気になる方も多いはずです。
食べ方や頻度を工夫すれば、健康リスクを抑えながら無理なく楽しむことができます。
さらに、ラーメンを食べた後の食事でバランスを調整することも忘れずに。



健康的な食生活の一部として、上手にラーメンを取り入れていきましょう。