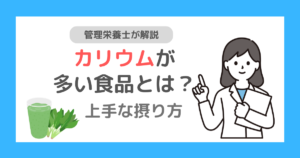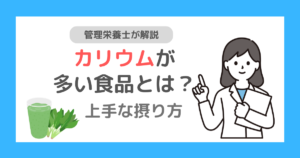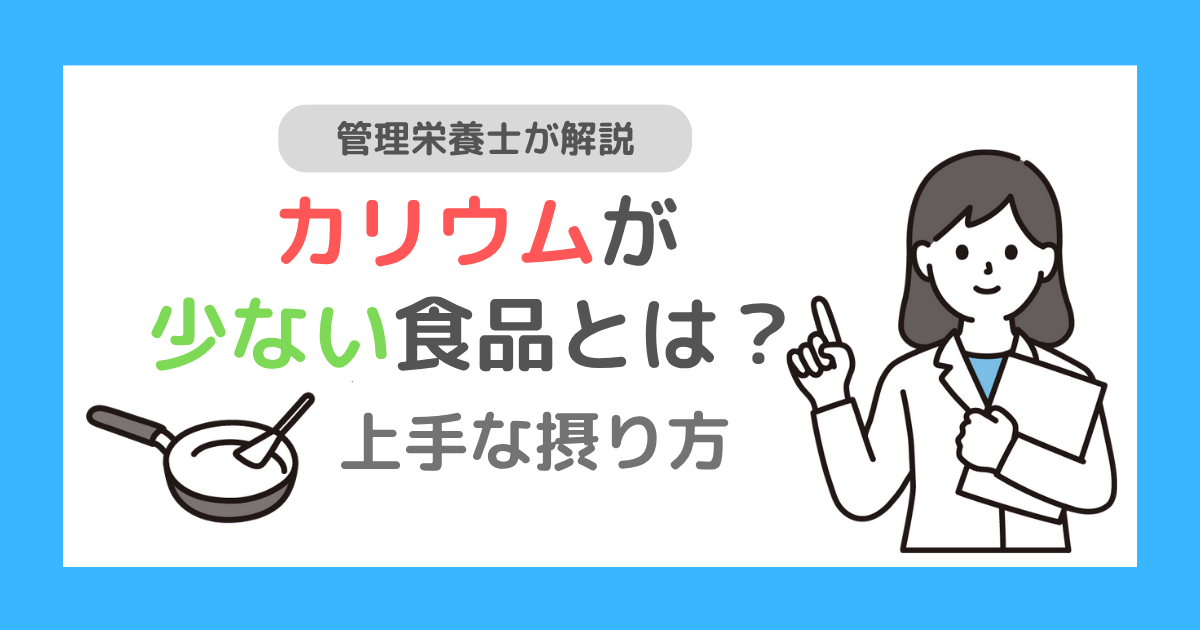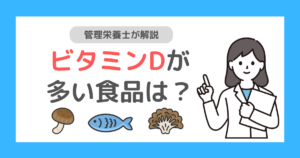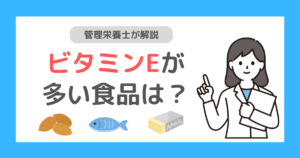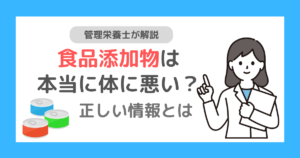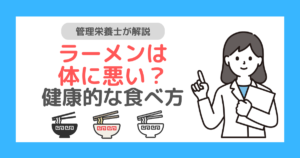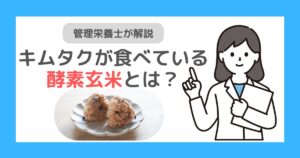- カリウムが少ない食べ物って何?
- どうやってカリウムを抑えればいいの?
そんな疑問をお持ちではありませんか?
カリウムは、健康な人にとっては積極的に摂りたい栄養素のひとつです。
しかし、腎臓に疾患がある方など、一部の方にとってはカリウムの摂りすぎが健康リスクとなり、制限が必要になることもあります。
とはいえ、カリウムが多い食品比べて、「カリウムが少ない食品」はあまり知られておらず、何を食べればいいのか分からず困ってしまう方も多いのではないでしょうか。
そこでこの記事では、管理栄養士の視点から、カリウムを控えたい方に向けて、カリウムが少ない食品の具体例、摂りすぎを防ぐポイントを分かりやすく解説します。

管理栄養士 こま
- 30代の管理栄養士
- 急性期病院3年・給食委託会社8年
- 病院(2施設)とクリニックで栄養指導経験
- 1日平均4万食提供の委託給食の献立作成を担当
- 関西・関東の病院を中心とした給食提供実績
この記事を読めば、カリウムの摂取を上手にコントロールするヒントがきっと見つかるはずです。
「何を食べればいいか分からない…」と感じている方は、ぜひ最後までご覧ください。
カリウムとは?体内での役割
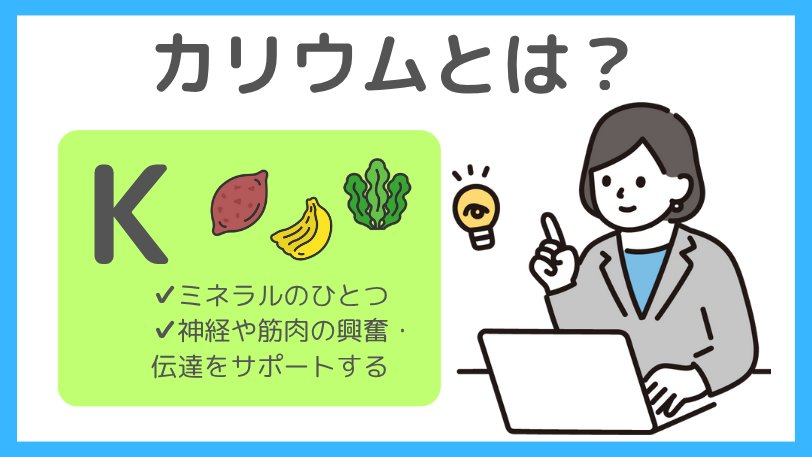
カリウムは、私たちの体に欠かせないミネラルの一種で、細胞の中に多く存在しています。ナトリウムとバランスを取りながら、体のさまざまな働きを支えています。
カリウムは具体的に、以下のような役割があります。
- 体内の浸透圧(細胞内外の水分バランス)を調整する
- 酸・塩基(pH)のバランスを保つ
- 神経や筋肉の興奮・伝達をサポートする
通常、カリウムは摂りすぎたとしても尿として排出されるため、腎機能が正常な場合は、過剰摂取による問題は起こりにくいとされています。
しかし、腎臓の働きが低下している場合は、注意が必要です。
実際に日本人の食事摂取基準(2025年版)では以下のように記載されています。
腎機能が正常であれば、普段の食事からのカリウム摂取によって代謝異常(高カリウム血症)を起こすことはない。CKDでは、ステージが進むにつれ、腎臓からのカリウム排泄量が減少し、また代謝性アシドーシスの合併によって高カリウム血症(血清カリウム値5.5mEq/L以上)を起こす頻度が上昇する。高度な高カリウム血症(血清カリウム値7.0mEq/L以上)は、不整脈による突然死の原因になる可能性があり、極めて危険である。「エビデンスに基づくCKD診療ガイドライン2023」では、血清カリウム値(mEq/L)を4.0以上5.5未満にコントロールすることを提唱している。
つまり、腎機能が低下していると、カリウムが排出されなくなり、不整脈による突然死などの命に関わる危険性があるということです。
そのため、腎機能が低下している人は、医師や管理栄養士の指導のもと、食事からのカリウム摂取量を適切にコントロールする必要があります。
制限が必要な場合の1日のカリウム摂取量は?
カリウムを制限したい人にとっての摂取量は、腎機能の程度によってその量が変わります。
CKDのガイドラインが定められており、ステージごとのカリウム量は以下の通りです。
| CKDステージ | カリウム(mg/日) |
| ステージ1~3a | 制限なし |
| ステージ3b | 2000mg以下 |
| ステージ4・5 | 1500mg以下 |
ただし、ここの数値はあくまで参考までとし、具体的な制限量については必ず医師や管理栄養士の指導のもと判断してください。
カリウムはいろいろな食品に幅広く含まれているため、1日1500mg以下にしようと思うと、意識的に制限をする必要があります。
カリウムが少ない食品とは?
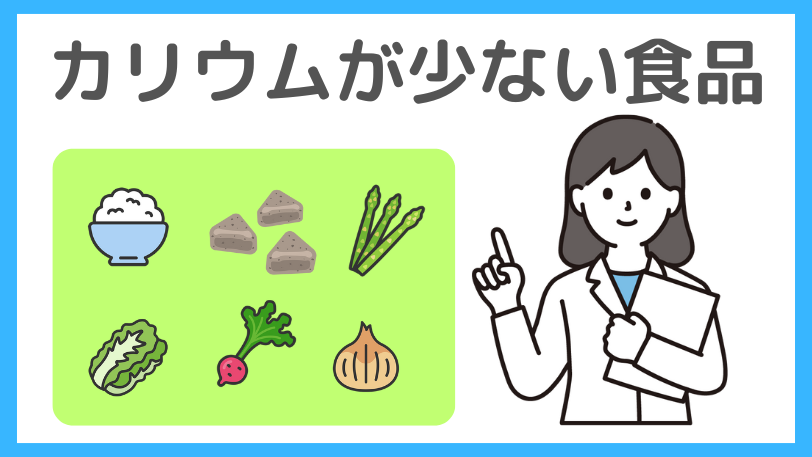
では、カリウムが少ない食品には、どのようなものがあるのでしょうか?
カリウムは、実は多くの食品に広く含まれている栄養素です。
そのため、カリウムの摂取量を抑えたい場合は、カリウムを多く含む食品を控えめにし、比較的少ない食品を選んで取り入れることが大切になります。
ここでは、各食品群の中で、比較的カリウムが少なめの食品をご紹介します。
これらの食材をうまく取り入れることで、日々の食事の中でカリウムの摂りすぎを防ぐことができるでしょう。
穀類
例えば、玄米は栄養価が高く健康的な食品ですが、カリウムの量も多くなります。
そのため、白米やうどんなどの白い穀類のほうが、比較的カリウムが少ないです。
穀類でカリウムが少ないものは以下の通り。
| 100g当たり | カリウム(mg) |
| 食パン | 86 |
| ゆでうどん | 9 |
| 精白米 | 89 |
 管理栄養士 こま
管理栄養士 こま穀類自体はそんなにカリウムが多くない食品です。
いも類
いも類はカリウムの含有量が多いので、摂取量に注意が必要です。
しかし、こんにゃく類はカリウムが少なく安心して食べられます。
いも類でカリウムが少ないものは以下の通り。
| 100g当たり | カリウム(mg) |
| 板こんにゃく | 33 |
| しらたき | 12 |



いもは、さつま芋(380mg)→じゃが芋(420mg)→長いも(430mg)→里芋(640mg)順でカリウムの含有量が多くなります。
豆類
豆類も比較的カリウムが多い食材ですが、選び方を少し変えるだけでも摂取量を控えることができます。
豆類でカリウムが少ないものは以下の通り。
| 100g当たり | カリウム(mg) |
| ゆで小豆缶詰 | 160 |
| こしあん | 35 |
| 水煮缶詰 大豆 | 250 |
| 木綿豆腐 | 110 |
| 油揚げ | 86 |
| 凍り豆腐 乾 | 34 |
カリウムは水に溶けやすい性質があるため、水煮缶を利用すると茹でる過程でカリウムが減少していることが多いです。 ただし、缶詰の煮汁にはカリウムが溶け出している可能性が高いため、汁ごと使うのは避けましょう。
あんこを使う場合は、粒あん(約160mg)よりも、カリウムが少ないこしあん(約35mg)を選ぶのがおすすめです。
豆腐は絹ごし(約150mg)よりも木綿(約110mg)の方がカリウムが少なめです。
種実類
種実類は全体的にカリウムが高いので量に注意が必要です。
種実類でカリウムが少ないものは以下の通り。
| 100g当たり | カリウム(mg) |
| くり甘露煮 | 75 |



アーモンドなどは760gもあります。量を決めて食べ過ぎないようにしましょう。
野菜類
カリウムが少ない野菜を知りたい方は多いのではないでしょうか。
野菜でカリウムが少ないものは以下の通り。(※は緑黄色野菜)
| 100g当たり | カリウム(mg) |
| アスパラガス 生※ | 270 |
| さやいんげん 生※ | 260 |
| うど 生 | 220 |
| スナップエンドウ 生※ | 160 |
| オクラ 生※ | 280 |
| かぶ 生 | 280 |
| キャベツ 生 | 190 |
| きゅうり 生 | 200 |
| 貝割れ大根 生※ | 99 |
| 大根 生 | 230 |
| たけのこ水煮缶詰 | 77 |
| 玉ねぎ 生 | 150 |
| 赤玉ねぎ 生 | 150 |
| チンゲン菜 生※ | 260 |
| 冬瓜 生 | 200 |
| ヤングコーン 生 | 230 |
| トマト 生※ | 210 |
| なす 生 | 220 |
| ゴーヤ 生 | 260 |
| 黄ニラ 生 | 180 |
| にんにくの芽 生※ | 160 |
| 長ねぎ 生 | 200 |
| 葉ねぎ 生※ | 260 |
| 白菜 生 | 220 |
| ラディッシュ 生 | 220 |
| ピーマン 生※ | 190 |
| みょうが 生 | 210 |
| 糸もやし 生 | 43 |
| 大豆もやし 生 | 160 |
| 緑豆もやし 生 | 79 |
| レタス 生 | 200 |
| わけぎ 生 | 230 |
| 冷ミックスベジタブル | 220 |
たけのこはカリウムが多い食材ですが、水煮缶詰を使うことでカリウムを抑えられます。缶詰の煮汁にはカリウムが溶け出している可能性が高いため、汁ごと使うのは避けましょう。
緑黄色野菜の中にはカリウムを多く含むものが多いですが、中にはカリウムの少ない種類もあります。上手に選べば、カリウムの摂取を控えながら、しっかりと緑黄色野菜を取り入れることができます。



野菜の中でもカリウムが少なめのものを紹介していますが、食べる量が多くなりすぎると過剰摂取につながる場合があるので、ご注意ください。
果実類
果物は野菜ほどカリウムを多く含んでいませんが、一度にたくさん食べてしまいやすいため、摂取量には注意が必要です。
果物でカリウムが少ないものは以下の通り。
| 100g当たり | カリウム(mg) |
| いちご 生 | 170 |
| いちじく 生 | 170 |
| 柿 生 | 170 |
| いよかん 生 | 190 |
| みかん 生 | 150 |
| オレンジ 生 | 180 |
| きんかん 生 | 180 |
| グレープフルーツ 生 | 140 |
| なつみかん 生 | 190 |
| はっさく 生 | 180 |
| ぶんたん 生 | 180 |
| すいか 生 | 120 |
| すもも 生 | 150 |
| 梨 生 | 140 |
| パイナップル 生 | 150 |
| びわ 生 | 160 |
| ぶどう 生 | 130 |
| ブルーベリー 生 | 70 |
| マンゴー 生 | 170 |
| 白桃 生 | 180 |
| やまもも 生 | 120 |
| ラズベリー 生 | 150 |
| りんご 生 | 120 |



果物は、缶詰を選ぶのもおすすめです!よりカリウムを抑えることができます。(シロップは✖)
きのこ類
きのこでカリウムが少ないものは以下の通り。
| 100g当たり | カリウム(mg) |
| ゆできくらげ | 37 |
| しいたけ 生 | 290 |
| なめこ 生 | 240 |
| まいたけ 生 | 230 |
海藻類
海藻類は基本的にカリウムが多い食品ですが、種類によってはカリウムが少ないです。
海藻類でカリウムが少ないものは以下の通り。
| 100g当たり | カリウム(mg) |
| うみぶどう 生 | 39 |
| ところてん | 2 |
| 寒天 | 1 |
| とさかのり | 37 |
| もずく | 2 |
| めかぶ 生 | 88 |



のりや昆布はカリウムが多いです。
飲み物
飲み物にもカリウムが多いものがあるので注意が必要です。
飲み物でカリウムが少ないものは以下の通り。
| 100g当たり | カリウム(mg) |
| 煎茶 浸出液 | 27 |
| 番茶 浸出液 | 2 |
| ほうじ茶 浸出液 | 1 |
| 玄米茶 浸出液 | 7 |
| ウーロン茶 浸出液 | 13 |
| 紅茶 浸出液 | 8 |
| 甘酒 | 14 |
| 麦茶 浸出液 | 6 |
お茶の中でも玉露(340mg)・昆布茶(580mg)はカリウムが多いです。
牛乳(150mg)・豆乳(190mg)・青汁(2300mg)・野菜ジュース(230mg)などもカリウムが含まれています。
コーヒー(65mg)はそれほど多くはありませんが、1日に何杯も飲むと摂取量が増えてしまう可能性があります。
カリウムを摂りすぎないためのポイント


カリウムを上手に減らすためにはいくつかのポイントがあります。
以下のポイントを意識して、適切なカリウム摂取を心がけましょう。
水に溶かす
カリウムは水に溶けやすい性質を持っています。この性質を利用することで、調理中に食材からカリウムを減らすことが可能です。
たとえば、野菜はしっかりとゆでる、または生で食べる前に水にしばらくさらすなどの方法が効果的です。ただし、ここで注意が必要なのは、ゆで汁やさらし水を料理に再利用しないことです。これらの水には、食材から溶け出したカリウムが多く含まれている可能性があります。
たとえば、味噌汁を食べるとき、「ゆでてあるから大丈夫」と思ってしまうかもしれません。しかし、味噌汁の汁そのものにカリウムが含まれているため、汁を飲むことでカリウムを摂取することになります。
カリウムをしっかり減らしたい場合は、ゆでたあとのゆで汁を捨て、新しい水で調理し直すことが重要です。少し手間はかかりますが、カリウムを減らすためには欠かせない一工夫です。



さらに効果的な方法として、食材を小さく切ることでカリウムが水に溶け出す面積を増やすといった工夫もおすすめです。
缶詰を利用する
食材には缶詰で売られているものもあります。缶詰を活用することで、通常の食材よりもカリウムの量を減らせる場合があります。
これも、カリウムの水に溶けやすい性質により、一部が缶詰の汁に溶け出しているためです。
例えば、以下は小豆の「ゆで」と「缶詰」のカリウム量の比較です。
| 100g当たり | カリウム(mg) |
| 小豆 ゆで | 430 |
| ゆで小豆缶詰 | 160 |
小豆はカリウムが多い食品の一つですが、通常のゆで調理ではまだ多く残っています。しかし缶詰では約35%のカリウム量にまで減少しており、制限が必要な方でも取り入れやすくなっています。
このように、カリウムの多い食材でも、缶詰を利用することで安心して食べられるケースがあります。
以下のような食品は、缶詰として販売されており、カリウムを抑えたいときに活用できます。
- 小豆
- 大豆
- 金時豆
- ひよこ豆
- レンズ豆
- たけのこ
- グリンピース
- コーン
- みかん
- パイナップル
- 桃
- 洋梨
- りんご
- ぶどう
- マンゴー
- さくらんぼ
※ トマト缶は中身と汁が混ざっていて、カリウム制限にはあまり向いていません。
ただし、肉や魚などの缶詰は、加工していてもカリウムがあまり減っていないことが多く、通常の食品と大きな違いはありません。そのため、これらは無理に缶詰にこだわる必要はないでしょう。
カリウムは控えすぎにも注意
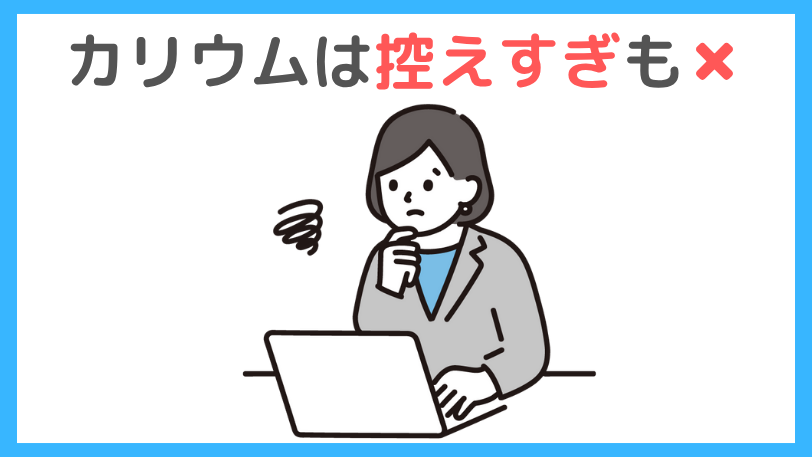
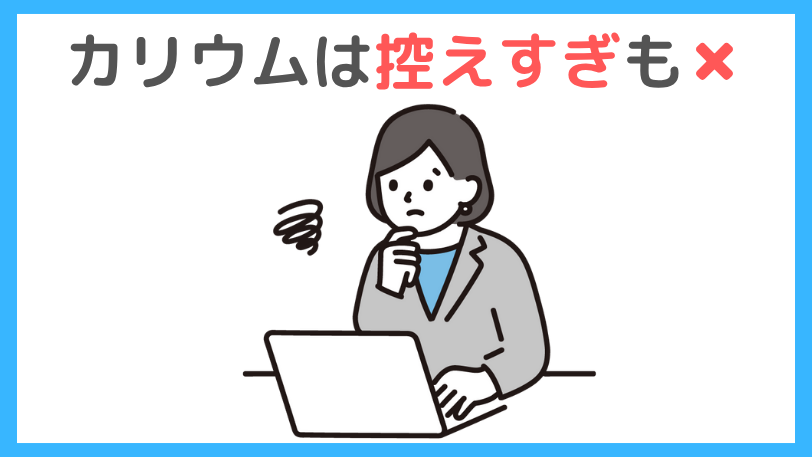
これまで、カリウムを減らす工夫や、カリウムの少ない食品の選び方についてご紹介してきました。
しかし、カリウムは「減らしすぎ」にも注意が必要です。
これは多すぎても少なすぎても、体に悪影響を及ぼす可能性があるためです。
私は過去に透析室で栄養指導をしていました。その際、カリウムが高くて悩んでいた方に対して、今回ご紹介したようなカリウムの少ない野菜や調理法を提案したことがあります。
その方はすぐに実践してくださり、血清カリウム値は見事に改善されました。
しかし、今度は逆に基準値を下回る(4.0未満)状態になってしまい、再び「控えすぎないように」とお伝えすることがありました。
このように、過剰な制限もリスクとなることがあります。
少し難しく感じられるかもしれませんが、ご自身の体調や検査結果に合わせて、無理のない範囲で調整していくことが大切です。
カリウムの制限量や対策は、必ず主治医や管理栄養士の指導のもと行ってください。
まとめ:カリウムは上手に抑えよう


この記事では、カリウムが少ない食品の選び方や摂りすぎを防ぐ工夫についてご紹介しました。
要点をまとめると以下の通り。
- 腎機能が低下している人は、カリウム制限が必要になることがある
- 制限の内容や量は、必ず医師や管理栄養士の指導に従うことが大切
- 血清カリウム値(mEq/L)は 4.0以上5.5未満が望ましい
- カリウムが少ない食品を選ぶことで、摂りすぎを防げる
- カリウムは水に溶けやすいため、調理の工夫で減らすことができる
- 一方で、控えすぎにも注意が必要
カリウムは、野菜や果物、豆類など多くの食品に広く含まれているため、意識しないと摂りすぎてしまうことがあります。腎機能に問題がある方にとっては、これが大きなリスクになる場合も。
「カリウムを気にすると、食べるものがない…」と感じている方も、今回ご紹介したようなカリウムが少ない食品や、減らす工夫を取り入れることで、食事の選択肢が広がるかもしれません。



ただし繰り返しになりますが、カリウムの制限は自己判断せず、必ず医療専門職の指導のもとで行いましょう。