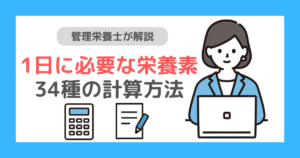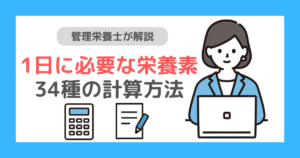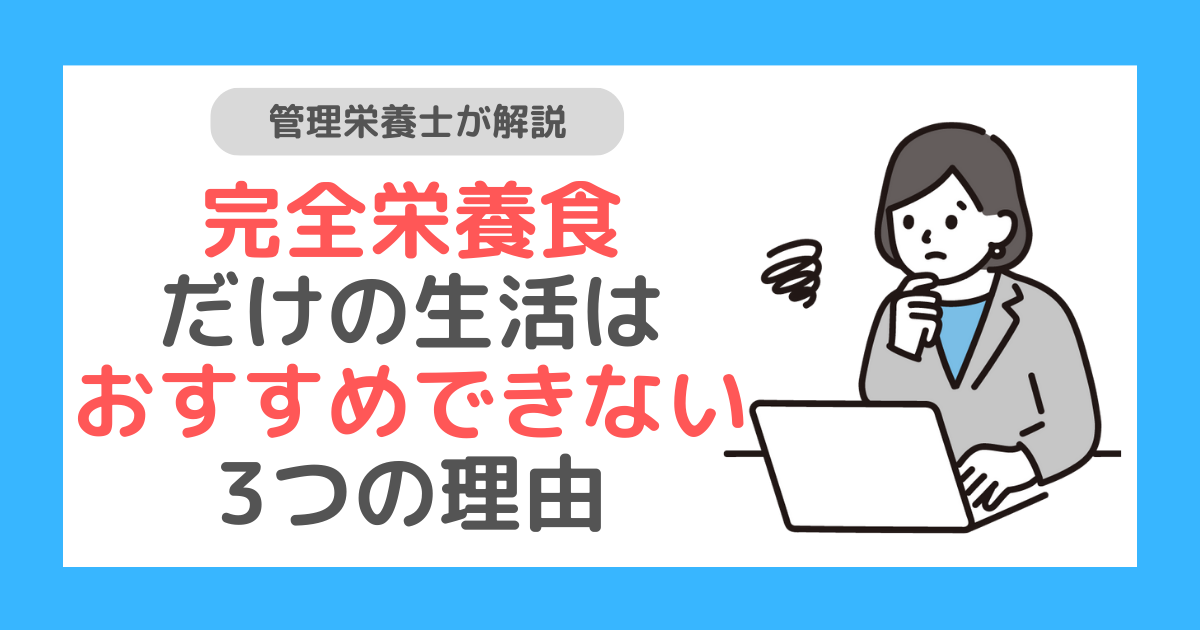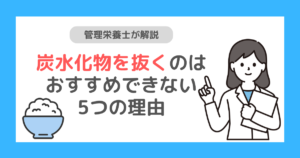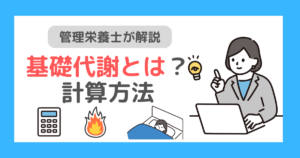- 完全栄養食って本当に体にいいの?
- これだけで生活しても大丈夫なの?
こういった疑問はありませんか?
最近、「完全栄養食」や「完全メシ」など、“完全”をうたう商品をよく見かけるようになりました。
「完全」と聞くと、これさえ食べていれば健康が保てるのでは?と思ってしまう方も多いのではないでしょうか。
でも、管理栄養士の立場から言うと、「完全栄養食だけの食生活」は決しておすすめできません。
確かに、便利で効率的な食品ではありますが、注意点もいくつかあります。
そこでこの記事では、管理栄養士の視点から、完全栄養食だけで生活はおすすめできない理由や使用時の注意点などを解説します。

管理栄養士 こま
- 30代の管理栄養士
- 急性期病院3年・給食委託会社8年
- 病院(2施設)とクリニックで栄養指導経験
- 1日平均4万食提供の委託給食の献立作成を担当
- 関西・関東の病院を中心とした給食提供実績
健康面に注意しながら利用したい人はぜひ最後まで見てください。
そもそも完全栄養食とは?
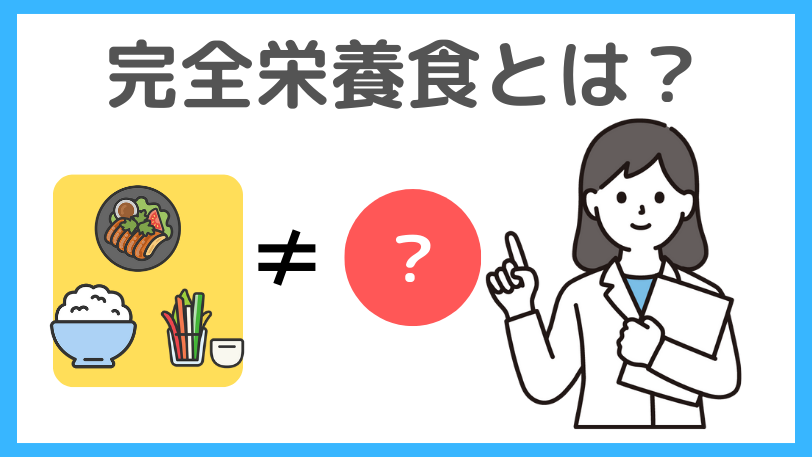
完全栄養食とは、一般的に「1食に必要なすべての栄養素をバランスよく摂取できる食品」のことを指します。
含まれる栄養素は、厚生労働省が策定する「日本人の食事摂取基準」に基づいて設定されており、多くの商品は1日の必要量の約1/3を1食で摂れるよう設計されています。
現在では、パン・麺類・菓子類・ドリンクタイプなど、さまざまな形状で市販されており、忙しい現代人の食事を手軽にサポートする食品として注目を集めています。
完全栄養食だけで生活はおすすめできない3つの理由
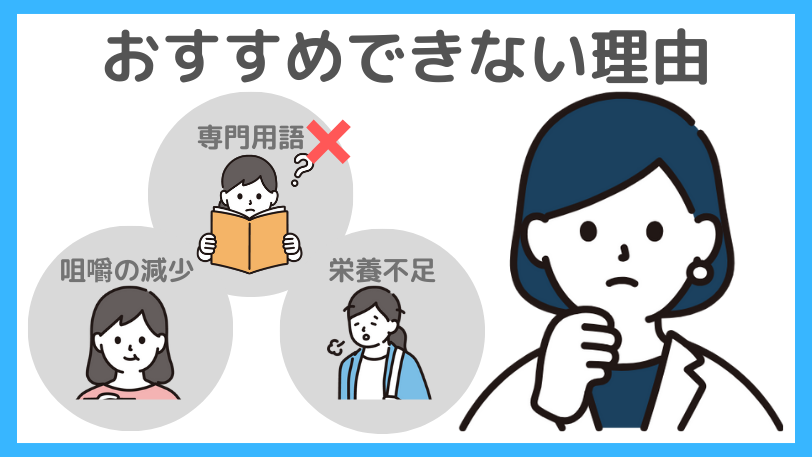
完全栄養食と聞くと、「完全に栄養が摂れる」、これだけとっていればOKというように感じてしまうこともあるかもしれません。
理由は次の通りです。
「完全栄養食」は栄養学的な専門用語ではない
まず理解しておきたいのは、「完全栄養食」という言葉は栄養学的・公的に定義された専門用語ではないという点です。
実際には、企業が自社商品を説明する際に使っているマーケティング用語として広まった表現にすぎません。
そのため、「完全栄養食」と聞くと、あたかもそれだけで完璧な栄養が摂れるように思えますが、その言葉を鵜呑みにして、完全栄養食だけに頼った食生活を続けるのは非常にリスクが高いと言えます。
たしかに、多くの製品は、厚生労働省が定める「日本人の食事摂取基準」に基づいて、1食に必要な栄養素を過不足なく含むように設計されています。
日本人の食事摂取基準には、以下のように記述されています。
3-1摂取源
食事として経口摂取される通常の食品に含まれるエネルギーと栄養素を対象とする。ただし、耐容上限量については、いわゆる健康食品やサプリメント(以下「通常の食品以外の食品」という。)由来のエネルギーと栄養素も含むものとする。耐容上限量以外の指標については、通常の食品からの摂取を基本とするが、…(中略)…
つまり、日本人の食事摂取基準はあくまで日常的に口にする“通常の食品”からの栄養摂取を前提としており、健康食品やサプリメント(=通常の食品以外)からの摂取は原則として想定されていません。
そのため、たとえ「日本人の食事摂取基準に準拠」と謳われていたとしても、完全栄養食はそもそも通常の食品とは異なる“特殊な形態の食品”。
実際に、令和6年7月の消費者庁の資料でも、「健康増進法第65条第1項」の「著しく人を誤認させるような表示をしてはならない」の例に、以下の記述がありました。
完全栄養等と称して健康維持に必要な栄養成分を全て不足なく含んでいるかのように誤認させる表示をしている場合
このように、「完全栄養食」という言葉には明確な定義がなく、その言葉の使い方にも注意喚起がなされているのです。
便利な存在ではありますが、過信して完全栄養食だけに頼った食生活を続けることは、現時点ではおすすめできません。
咀嚼不足による健康リスク
完全栄養食だけに頼った食生活になると、圧倒的に咀嚼回数が減ってしまう傾向があります。
咀嚼回数が減ると、▼以下のような健康リスクの可能性があります。
唾液の分泌が減少し、口腔や消化器に悪影響
咀嚼によって分泌される唾液には、消化を助ける酵素が含まれており、口の中の洗浄・殺菌の働きも担っています。咀嚼が不足すると、これらの効果が得られず、口臭・虫歯・胃腸への負担が増す可能性があります。
あごや口周りの筋肉が衰える
噛む動作は、あごの発達や顔まわりの筋力維持にも欠かせません。咀嚼の少ない食生活を長期間続けることで、あご関節の機能低下や顔周りの筋力低下に繋がる可能性があります。
満腹感を得にくく、過食のリスクが高まる
噛むことは、脳に「満腹感」を伝える働きもあります。噛む回数が少ないと、食事をしているという実感が得られにくくなり、結果として食べ過ぎや間食の増加に繋がることもあります。
このように、咀嚼という行為は単なる「食べる手段」ではなく、健康維持において重要な役割を果たしています。完全栄養食を過度に頼ることで、こうした自然な生理機能が損なわれる可能性がある点には注意が必要です。
栄養が不足する可能性
「完全栄養食」と謳われている製品であっても、カロリーや脂質が十分に含まれていない場合も多く、逆に栄養不足に陥るリスクがあります。
とくに、活動量が多い人や体格の大きい人にとっては、必要なエネルギーを補いきれないことも少なくありません。
また、完全栄養食はあくまで「主要な栄養素(タンパク質、ビタミン、ミネラルなど)」を数値的にバランスよく配合した食品ですが、自然の食品が持つ複雑な栄養成分までは再現されていないのが実情です。
たとえば、▼以下のような成分は、完全栄養食ではほとんどカバーされていません。
- フィトケミカル(ポリフェノール、カロテノイドなどの植物由来成分)
- 多様な種類の食物繊維(水溶性・不溶性のバランスや、食品由来の違い)
- 発酵食品由来の微生物や代謝物(腸内環境に良い影響を与える可能性がある成分)
これらの成分は、病気の予防や体調の維持に関わる重要な役割を果たしていると考えられており、単に「必須栄養素が足りている」というだけでは不十分な場合があります。
そのため、完全栄養食だけの食生活では、自然な食品が持つ栄養を十分に取り入れることが難しくなるという点にも注意が必要です。
完全栄養食を上手に取り入れる方法

では、完全栄養食はどのように取り入れるのが良いのでしょうか?
大切なのは、「便利さに頼りすぎないこと」と「通常の食事と上手に組み合わせること」です。
以下に、完全栄養食を効果的に活用するための具体的な方法を紹介します。
忙しい日の“置き換え食”として使う
時間がない朝や、外食が続いて栄養バランスが気になるときなどに、一時的な置き換え食として完全栄養食を活用するのは有効です。
特に朝食や間食など、手軽に済ませたいタイミングで取り入れれば、時間と栄養の両方を効率よくカバーできます。
通常の食事と組み合わせて使う
完全栄養食には、基本的な栄養素は含まれていても、食物の多様性や微量成分は十分でない場合があります。
そのため、単品で済ませず、野菜・果物・発酵食品などの食材と組み合わせて摂ることが大切です。
たとえば、主食タイプ(パンや麺など)の完全栄養食であれば、普段通りに肉・魚・野菜・きのこ類などを添えることで、よりバランスの取れた食事になります。
非常食や備蓄用として活用する
長期保存が可能な完全栄養食は、災害時や体調不良時など、通常の食事が難しい状況でも役立つ備蓄食品として活用できます。
栄養バランスが設計されているため、偏りがちな非常食の中でも、比較的安心して取り入れられるのが特長です。
完全栄養食は便利で合理的な食品ですが、万能ではありません。日常の中で適切なタイミングに活用しながら、多様な食品との組み合わせを意識することで、健康的な食生活のサポート役として上手に取り入れることができます。
完全栄養食を利用する際の注意点
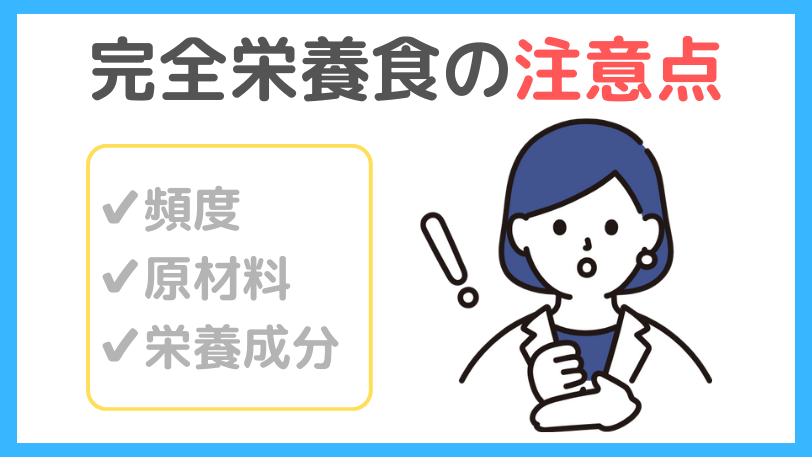
完全栄養食は、忙しいときや栄養バランスが気になる場面で便利に使える食品ですが、使い方を誤ると、かえって健康に悪影響を及ぼす可能性もあります。
以下に、利用する際に意識しておきたい主な注意点を紹介します。
利用頻度は控えめに
完全栄養食は「時短・効率」の面で優れた食品ですが、あくまで補助的に活用するのが基本です。
毎食のように頼ってしまうと、咀嚼不足や腸内環境の乱れ、自然食品から得られる微量栄養素の欠乏などが起こる可能性があります。
「忙しい日だけ」「朝食の代わりに週数回」など、無理のない頻度で取り入れることが、健康を損なわずに活用するコツです。
食生活がすでに整っている人は、無理に取り入れない
すでにバランスの良い手作りの食事をしている方は、無理に完全栄養食を取り入れる必要はありません。
むしろ、自然な食材から得られるフィトケミカルや食物繊維、多様な栄養素を維持するためにも、今の食生活を続けることが理想的です。
原材料の質をチェックする
完全栄養食は加工食品である以上、製品ごとの原材料の質に差があります。
選ぶ際は、なるべく以下のような製品を選ぶのがおすすめです。
- できるだけ素材そのものを使っている(○○粉末/抽出物ばかりでない)
- 人工甘味料や保存料が少ない
- 食品添加物の量が抑えられている
体に入れるものだからこそ、「原材料欄」はしっかり確認しておきましょう。
栄養成分のバランスも確認する
「完全栄養」と書かれていても、実際には製品ごとに栄養バランスにばらつきがあります。
とくに以下の項目はチェックしておくと安心です。
カロリーが不足していないか?
→ 活動量の多い人にとっては、エネルギーが足りない場合もあります。
脂質が極端に少なくないか?
→ 健康に必要な脂質もあるため、ゼロに近いものは注意。
飽和脂肪酸の量が多すぎないか?
→ 飽和脂肪酸の基準は、「積極的に摂りたい量」ではなく、「摂りすぎを控えるための上限値」として設定されています。過剰に摂取すると、動脈硬化や心血管疾患のリスクを高める可能性があるため注意が必要です。「基準を満たしている=良いこと」とは限らないため、むしろ抑えることが望ましい栄養素だと理解しておきましょう。
塩分は多すぎないか?
→塩分(ナトリウム)も同様に、摂取量を抑えることが推奨されている栄養素です。摂りすぎは高血圧や生活習慣病のリスクを高める要因になるため、特に注意が必要です。完全栄養食を選ぶ際は、1食あたりの塩分量が2~2.5g以下を目安にすると安心です。
できるだけ咀嚼が必要な商品を選ぶ
完全栄養食には、さまざまな形状の商品があります。選ぶ際には「噛んで食べる」ことが求められる固形タイプの製品をできるだけ選ぶようにしましょう。
流動性のあるものは噛まずに飲み込んでしまうことが多いので注意です。
まとめ:完全栄養食だけに頼らず、上手に利用しよう

この記事では、完全栄養食だけで生活はおすすめできない理由や使用時の注意点などを解説しました。
要点をまとめると以下の通り。
- 「完全栄養」食は栄養学的な専門用語ではない
- 咀嚼不足による健康リスクが起こりやすい
- 完全栄養食だけだと栄養の偏りや不足が起こる可能性もある
- 利用する場合は、忙しい日などに“補助的”に使うのが理想的
完全栄養食は、手軽に栄養を補える便利な選択肢ではありますが、それだけで健康が保てるわけではありません。
大切なのは、「主食・主菜・副菜がそろったバランスの良い食事」を基本としながら、ライフスタイルに合わせて、無理なく上手に取り入れることです。
 管理栄養士 こま
管理栄養士 こま使用する際は、この記事で紹介した注意点を参考に、賢く・安全に活用していきましょう。