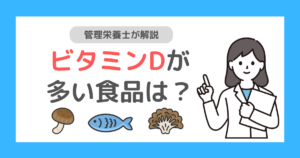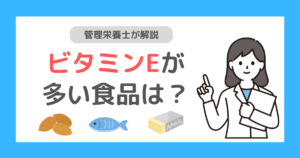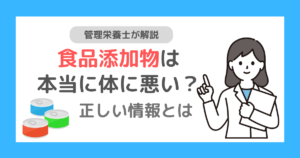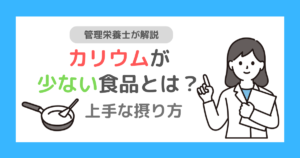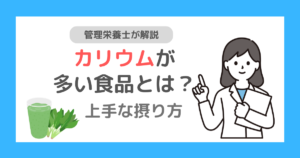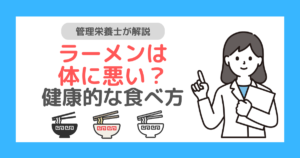- 最近、野菜をあまり食べていない気がする…
- 野菜って、具体的にどんな栄養があるの?
- 毎日ちゃんと野菜を摂るコツが知りたい
こんな風に感じたことはありませんか?
野菜が健康に良いことは、誰もが知っている事実です。
しかし、実際に1日に必要な量をしっかり摂れている人は、意外と少ないのが現実です。
野菜が不足すると、ビタミンやミネラル、食物繊維などが足りなくなり、肌荒れや便秘、疲れやすさなど、さまざまな不調につながることもあります。
そこでこの記事では、野菜の栄養や種類、上手な摂り方について、管理栄養士の視点から解説します。

管理栄養士 こま
- 30代の管理栄養士
- 急性期病院3年・給食委託会社8年
- 病院(2施設)とクリニックで栄養指導経験
- 1日平均4万食提供の委託給食の献立作成を担当
- 関西・関東の病院を中心とした給食提供実績
「野菜をもっと効率よく摂取したい!」という方は、ぜひ最後までチェックしてみてください。
野菜に含まれる主な栄養素とその働き
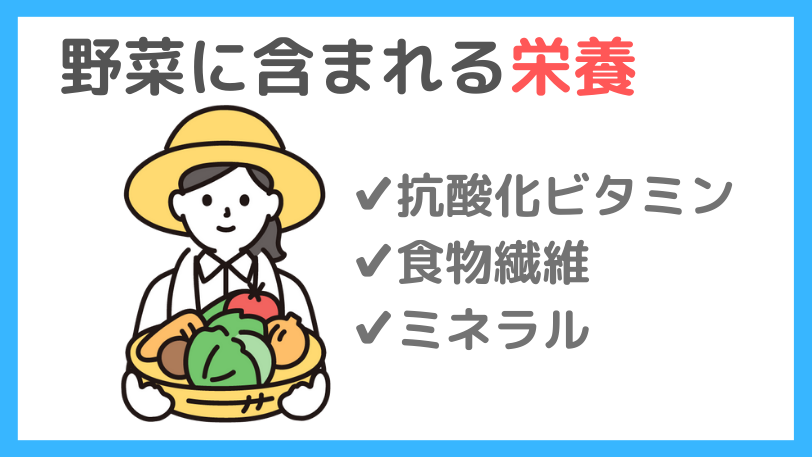
野菜は、抗酸化ビタミン、食物繊維、カリウム、カルシウム源として重要な食品です。
具体的に注目したい栄養素は以下の通り。
- 食物繊維
- カリウム
- ビタミンA
- ビタミンC
- 葉酸
食物繊維
野菜には、食物繊維が豊富に含まれています。
食物繊維は「第6の栄養素」とも呼ばれ、以下の健康効果があります。
- 腸内環境を整える
- 血糖値の上昇を抑える
- コレステロールを下げる
食物繊維には、大きく分けて水溶性食物繊維と不溶性食物繊維の2種類があります。
水溶性食物繊維:腸の中でゲル状になり、糖の吸収をゆるやかにする、コレステロールの排出を助ける働きがあります。
不溶性食物繊維:腸を刺激して便通を促すほか、老廃物の排出をサポートしてくれます。
野菜にはこの両方の食物繊維がバランスよく含まれています。特にごぼう、ブロッコリー、枝豆、オクラ、モロヘイヤなどが豊富です。
毎日の食事にしっかり野菜を取り入れることで、腸内環境が整い、便秘予防や美肌効果にもつながります。
▼以下は食物繊維が比較的多い野菜です。可食部100g当たりの栄養価です。
| 食物繊維の多い野菜 | 食物繊維(g)※ |
| らっきょう 生 | 20.7 |
| グリンピース 生 | 7.7 |
| しそ葉 生 | 7.3 |
※プロスキー変法測定値
 管理栄養士 こま
管理栄養士 こま食物繊維は植物性食品に多く含まれています。
もっと詳しくはこちら【食物繊維とは】
カリウム
野菜には、カリウムというミネラルも多く含まれています。カリウムは、体内の余分なナトリウム(塩分)を排出し、血圧を下げる働きがある栄養素です。
特に、外食や加工食品で塩分を摂りすぎがちな現代人にとって、カリウムは欠かせない栄養素です。
カリウムをしっかり摂ることで、以下のような効果が期待できます。
- むくみの予防・改善
- 高血圧の予防
- 筋肉や神経の正常な働きのサポート
ほうれん草・小松菜・モロヘイヤ・アボカド・じゃがいも・さつまいもなどに多く含まれています。
▼以下はカリウムが比較的多い野菜です。可食部100g当たりの栄養価です。
| カリウムの多い野菜 | カリウム(mg) |
| ふだんそう(スイスチャード) | 1200 |
| パセリ | 1000 |
| ほうれん草 | 690 |
ただし、カリウムは水に溶けやすい性質があるため、ゆでると一部が流れ出てしまいます。スープにする、蒸す、電子レンジ調理を活用するなど、調理方法を工夫すると効率よく摂取できます。



腎機能が気になる方はカリウム摂取には注意してください。
ビタミンA
野菜には、ビタミンAのもととなる「β-カロテン」が豊富に含まれています。β-カロテンは体内で必要に応じてビタミンAに変わり、目・皮膚・粘膜の健康維持や、免疫力アップに役立つ栄養素です。
特に次のような働きがあります。
- 目の乾燥や疲れを防ぐ
- 肌や喉などの粘膜を守る
- 風邪や感染症の予防に役立つ
にんじん・モロヘイヤ・豆苗・ほうれん草・春菊などに多く含まれています。
▼以下はビタミンAが比較的多い野菜です。可食部100g当たりの栄養価です。
| ビタミンAの多い野菜 | ビタミンA(μg)※ |
| しそ葉 生 | 880 |
| モロヘイヤ 生 | 840 |
| にんじん 生 | 720 |
※レチノール活性当量
β-カロテンは油と一緒に摂ると吸収率がアップします。



ごま油やオリーブオイルで炒めたり、ドレッシングをかけたりするのもおすすめです。
ビタミンC
野菜の中でも特に注目したいのが、ビタミンCです。
ビタミンCは、肌の健康を保つ・免疫力を高める・ストレスに強くなるなど、幅広い効果をもつ栄養素です。
主な働きは次の通り。
- コラーゲンの生成を助け、肌や血管の健康を維持する
- 抗酸化作用により、老化や生活習慣病の予防に役立つ
- 鉄の吸収をサポートして貧血予防に貢献
- 風邪などの感染症予防にも◎
パプリカ・ブロッコリー・菜の花・じゃがいもなどに多く含まれています。果物だと、キウイやいちごもビタミンCが豊富です。
▼以下はビタミンCが比較的多い野菜です。可食部100g当たりの栄養価です。
| ビタミンCの多い野菜 | ビタミンC(mg) |
| ミニパプリカ 生 | 200 |
| 芽キャベツ 生 | 160 |
| ブロッコリー 生 | 140 |
ビタミンCは熱に弱く、水に溶けやすい性質があるため、調理法に注意が必要です。



なるべく生で食べる、蒸す、スープにして煮汁ごと食べるなどの工夫で、損失を防ぎましょう。
ビタミンについて詳しくはこちら【ビタミンとは】
葉酸
野菜には、葉酸というビタミンB群の一種も多く含まれています。
葉酸は、細胞の生まれ変わりを助けたり、赤血球の生成をサポートする大切な栄養素です。
特に次のような働きがあります。
- 妊娠初期の胎児の発育に必要不可欠(神経管閉鎖障害のリスクを減らす)
- 赤血球をつくるのを助け、貧血予防に役立つ
- 細胞の新陳代謝をサポート
葉酸は、妊活中や妊娠初期の女性には特に重要とされていて、厚生労働省も積極的な摂取を推奨しています*1。(サプリメントなどから葉酸を400μg/日摂取)
ほうれん草・春菊・アスパラガス・枝豆・ブロッコリーなどに多く含まれています。
▼以下は葉酸が比較的多い野菜です。可食部100g当たりの栄養価です。
| 葉酸の多い野菜 | 葉酸(μg) |
| 菜の花 生 | 340 |
| えだまめ 生 | 320 |
| モロヘイヤ 生 | 250 |
葉酸は、水溶性ビタミンのため、茹でると水に流れ出てしまう点に注意が必要です。



なるべく蒸す・電子レンジ加熱・スープにして煮汁ごと摂るのがおすすめです。
野菜の種類は2つ!緑黄色野菜と淡色野菜


野菜は大きく分けて、緑黄色野菜と淡色野菜の2種類に分類されます。
緑黄色野菜とは、可食部100gあたりにカロテンが600μg以上含まれている野菜のことです。ただし、それ以下でも日常的にカロテンの供給源となるものは緑黄色野菜に分類されています。
含まれる栄養素や役割が異なるため、緑黄色野菜と淡色野菜の両方をバランスよく摂取することが大切です。
ここでは、それぞれに該当する代表的な野菜をご紹介します。
緑黄色野菜
緑黄色野菜は、色が濃く、栄養価が高いのが特徴です。特にβ-カロテン(ビタミンAの前駆体)を多く含み、皮膚や粘膜の健康、免疫力の維持に役立ちます。
主な緑黄色野菜*2
- アスパラガス
- いんげん豆
- 豆苗
- さやえんどう
- オクラ
- 南瓜
- 水菜
- 小松菜
- ししとう
- しそ
- 春菊
- 貝割れ大根
- チンゲン菜
- トマト
- 菜の花
- にら
- にんじん
- ネギ
- パクチー
- ピーマン(青・赤・オレンジ)
- ブロッコリー
- ほうれん草
- 三つ葉
- モロヘイヤ
- リーフレタス
- サニーレタス
- サラダ菜
- サンチュ



少しマイナーな野菜は除外しています。ここにない野菜が必ずしも淡色野菜とは限りません。
淡色野菜
淡色野菜は、緑黄色野菜に分類されない野菜のことを指します。色が比較的薄く、カロテン含有量が少ないのが特徴ですが、食物繊維やカリウムなどを豊富に含むものも多い野菜です。
主な淡色野菜
- キャベツ
- レタス(一般的な玉レタス)
- もやし
- 大根
- きゅうり
- 白菜
- かぶ
- たまねぎ
- セロリ
- なす
- れんこん
- ごぼう
- 長ねぎ(白い部分)
- カリフラワー
淡色野菜は、食感やボリュームを加える役割も担っています。



食べている野菜が、緑黄色野菜・淡色野菜のどちらかに注目してみましょう。
野菜は1日350gを目標に


厚生労働省が推進している「健康日本21(第三次)」では、野菜は1日350gを目安に摂取することが推奨されています。この目標は、食物繊維やカリウムの摂取を考慮して設定されています。
350gのうち、120gは緑黄色野菜からとることが望ましいです。



野菜の1/3は緑黄色野菜から摂ることを意識しましょう。
日本人の野菜摂取量は不足気味
日本人は、野菜摂取量が不足しています。
令和5年の国民健康・栄養調査によると、野菜の1日平均摂取量は256g。
1日350gを目指すためには、意識して野菜を多く取り入れることが大切です。
1日350gの実際の量
では野菜を1日350g摂るためには、実際にどれくらいの量を食べれば良いのでしょうか?
目安として、以下のような量を参考にしてみてください。
| 野菜の料理 | 野菜の量 | |
| 朝食 | サラダ70g 味噌汁30g | 100g |
| 昼食 | 焼きそば(具) | 120g |
| 夕食 | お浸し70g 煮物60g | 130g |
| 合計 | ー | 350g |
1日の野菜摂取量350gをしっかり摂るためには、毎食100g以上は野菜を摂りたいです。
しかし、実際にはこの量を摂れていない方が多いのではないでしょうか。
特に、朝は忙しくて野菜を摂る時間がないという人は多いと思います。



まずは、毎食必ず野菜を取り入れることを目標にして、少しずつ取り組んでいくことをおすすめします。
野菜を上手に摂る5つのコツ


野菜を摂るべきだと分かっていても、傷みやすかったりして、なかなか継続するのが難しいと感じる方も多いですよね。
普段の食事で野菜を上手に摂るためのコツを5つご紹介します。
調理でかさを少なくする
野菜を1日350g摂取するためには、野菜のかさを少なくしてたくさん摂れるように工夫しましょう。
生野菜は簡単に摂れる上、栄養の損失も少ない食べ方です。しかしすべての野菜を生サラダで摂ろうとすると、1日350gを達成するのは難しいかもしれません。
加熱するとかさが減り、たくさん食べやすくなります。野菜にもよりますが、加熱することで1/2程度にかさが減ることも多いです。
スープやお浸し、煮物など、加熱調理で野菜のかさを減らし、効率よく摂取できるようにしましょう。



私たち管理栄養士は、食事指導のとき「生野菜なら両手一杯、加熱した野菜なら片手1杯を目安に摂りましょう」(一食分)とお伝えすることが多いです。
メイン料理に野菜をたくさん入れる
野菜を摂りやすくするためには、メイン料理にたくさんの野菜を取り入れるのも一つの方法です。
野菜と言えば、サラダや小鉢に入った単品の野菜を思い浮かべることが多いですが、野菜が苦手な方や普段からあまり摂っていない方には、少しハードルが高いかもしれません。
そこで、メイン料理に野菜をたっぷり使うことで、肉や魚と一緒に野菜を摂ることができるので、よりおいしく食べることができます。調理の負担も軽くなります。
例えば、▼以下のようなメニューがあります。
筑前煮、回鍋肉、チンジャオロース、酢豚、豚肉の野菜炒め、鶏肉のオイスター炒め、八宝菜、野菜カレー、野菜たっぷり肉団子煮込み、牛肉のトマト煮込み、チャプチェ、ゴーヤチャンプルー、マーボーナス、鶏肉と白菜のクリーム煮、焼きそば、チャーハン、お好み焼き、白身魚の根菜あんかけ、タラの野菜蒸し、ぶり大根…



できるだけさまざまな種類の野菜を使って、メイン料理と一緒に野菜をしっかり摂りましょう!
茹でるよりも蒸す・炒める
野菜の栄養を逃さず摂るためには、ゆでるよりも蒸す・炒めるがおすすめです。
野菜には、水に溶けやすい「水溶性ビタミン」が多く含まれており、茹でると栄養が水に流れ出てしまいやすくなります。
次のような調理法がおすすめです。
- 蒸す
- 電子レンジで加熱する
- 炒める
- スープにして汁ごと食べる
これらの方法を取り入れることで、野菜に含まれるビタミンをより効率的に摂取することができます。
旬の野菜を選ぶ
野菜を選ぶ際は、季節を意識して「旬の食材」を選ぶことも大切です。
実は、同じ野菜でも、旬の時期とそうでない時期では栄養価に違いがあります。
例えば、ほうれん草の栄養価を比べてみましょう。
| 栄養成分(100g当) | 夏採り | 冬採り(旬) |
| エネルギー(kcal) | 18 | 18 |
| ビタミンC(mg) | 20 | 60 |
ほうれん草の旬は冬です。
旬の野菜は栄養価が高く、効率的に栄養を摂ることができます。旬の時期は野菜の価格も比較的安くなるため、家計にもやさしいというメリットもあります。
最近はスーパーなどで1年中手に入る野菜も多いですが、ぜひ季節に注目して旬の野菜を取り入れましょう。



旬の野菜を取り入れることで、種類が偏らずいろんな野菜を食べることができます。
冷凍野菜を使う
野菜を効率よく摂取するためには、冷凍野菜を上手に取り入れるのもおすすめです。
冷凍食品に対して「体にあまり良くない」というイメージを持つ方もいるかもしれませんが、冷凍野菜にはそのような心配はほとんどありません。
多くの冷凍野菜は、旬の時期に収穫された新鮮な野菜を急速冷凍して作られており、季節外れの野菜よりもビタミンなどの栄養価が高い場合もあります。
また、「添加物が入っているのでは?」と気にされることもありますが、冷凍野菜は急速冷凍によって保存性を高めているため、基本的に添加物は使われていません。安心して利用できます。
生野菜は傷みやすく買い置きが難しいため、忙しい日が続くと野菜不足になりがちです。冷凍野菜を常備しておけば、炒め物やスープなどにすぐ使えて便利です。



歯ごたえが気になりにくいスープなどに利用するのがおすすめ。
野菜ジュースも上手に活用
野菜をしっかり摂るためには、基本的には生の野菜や調理した野菜を食事から摂取することが大前提です。
しかし、忙しい朝や外出時など、どうしても野菜を摂りにくい場面もありますよね。そんなときには、野菜ジュースを補助的に取り入れるのも一つの方法です。
農林水産省の食事バランスガイドでも、野菜ジュースは補助的な食品として位置づけられています*3。また、食事の前に野菜ジュースを飲むことで、食後の血糖値の上昇を抑える効果があるという研究報告もあります*4。
ただし、野菜ジュースを選ぶ際にはいくつか注意点もあります。
野菜のみで作られた甘くないタイプを選びましょう。果汁の割合が多いものは糖分も多くなります。
あくまで不足分を補う「サポート」として活用するのがポイント。野菜ジュースだけに頼るのは×。
毎日の野菜摂取を無理なく続けるためにも、ライフスタイルに合わせて野菜ジュースを上手に取り入れていきましょう。
まとめ:野菜で毎日元気に!まずは+1皿から


この記事では、野菜の栄養や種類、効果的な摂り方について解説してきました。
ポイントをまとめると、以下の通りです。
- 野菜は、抗酸化ビタミン・食物繊維・カリウムなどが豊富
- 1日に350gの野菜摂取を目指す
- そのうち1/3は緑黄色野菜から摂るのが理想的
- 加熱調理をうまく活用して、かさを減らして食べやすくする工夫を
野菜が体に良いことは多くの人が知っていますが、実際に1日350gをしっかり摂れている人は少ないのが現状です。
本記事で紹介したちょっとしたコツを参考に、無理なく日々の食事に野菜を取り入れていきましょう。



まずは1日1皿野菜を増やすことから始めましょう。


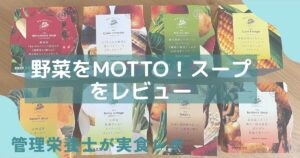
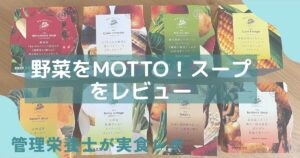




参考文献(2025年5月22日参照)
- *1:神経管閉鎖障害の発症リスク低減のための妊娠可能な年齢の女性等に対する葉酸の摂取に関わる適切な情報的きょうの推進について|厚生労働省
- *2:「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」の取扱いについて|厚生労働省
- *3:SV計算の難しいもの|農林水産省
- *4:“野菜ジュースファースト”の血糖値上昇抑制効果はベジタブルファーストと同等であることが判明!|カゴメ株式会社 経営企画本部 経営企画室
栄養価は、すべて日本食品標準成分表2020年版(八訂)より引用しています。