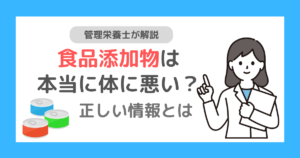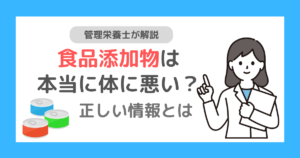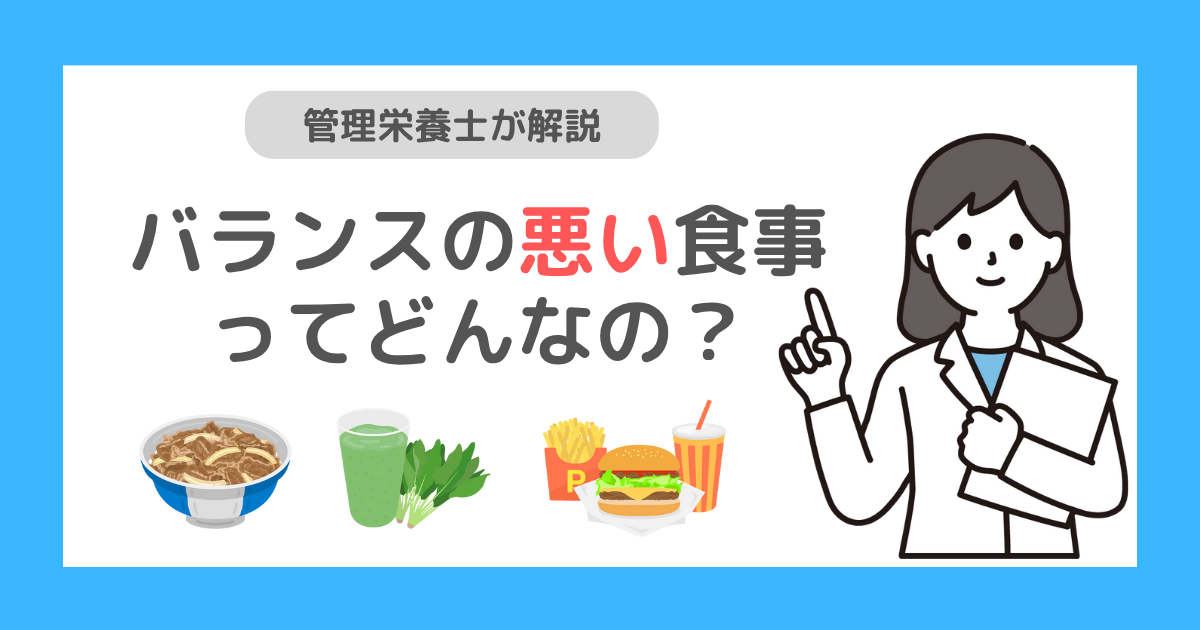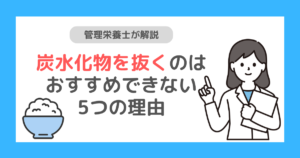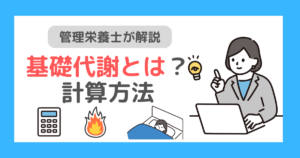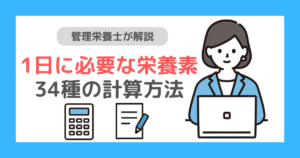- バランスの悪い食事ってどんなもの?
- 自分の食事は大丈夫?
- 続けると体にどんな影響があるの?
こんな疑問を感じていませんか?
「食事はバランスが大事」とよく言われますが、実際にどんな食事がバランスが悪いのか、よくわからない…という方も多いのではないでしょうか。
「自分の食生活、もしかして偏ってる?」と不安に思うこともありますよね。
実は、バランスの悪い食事を続けていると、将来的に生活習慣病などのリスクが高まる可能性もあります。だからこそ、日々の食事の中で、少しでもバランスを意識することがとても大切なんです。
そこでこの記事では、管理栄養士の視点から、
- バランスの悪い食事の具体例
- 健康に与える影響
- 今日からできるバランスの整え方のコツ
などをわかりやすく解説します。

管理栄養士 こま
- 30代の管理栄養士
- 急性期病院3年・給食委託会社8年
- 病院(2施設)とクリニックで栄養指導経験
- 1日平均4万食提供の委託給食の献立作成を担当
- 関西・関東の病院を中心とした給食提供実績
「今の食生活、ちょっとヤバいかも…」と感じている方は、ぜひ最後まで読んでみてください。
家族の栄養バランスが心配な方へ
おいしさで人気のオイシックスなら
買い出しなしで健康的な夕食に!

\ 初めての方限定!税込2980円! /
※定期購入ではなく、1回限りのセット
バランスの悪い食事の具体例5つ

バランスの悪い食事は、主に以下の5つのパターンがあります。
- 炭水化物に偏った食事
- たんぱく質に偏った食事
- 野菜が一切ない
- 野菜や果物のみ
- アルコール・ジュース・菓子だけ
例①:炭水化物に偏った食事

まず1つ目は、炭水化物に偏った食事です。これはついやってしまいがちなパターンです。というのも、飲食店のセットメニューなどでよく見かける組み合わせに多く含まれているからです。
例えば、以下のような、主食同士を組み合わせたメニューが典型的です。
- ラーメン + 白ご飯
- うどん + おにぎり
- パスタ + パン
これらはどれも炭水化物が中心となっており、栄養バランスが炭水化物に大きく偏ってしまうことになります。
例②:たんぱく質に偏った食事

2つ目は、たんぱく質に偏った食事です。
健康志向の高まりや筋トレブームの影響で、意識的にたんぱく質を多く摂ろうとする人が増えています。
もちろん、たんぱく質は身体づくりに欠かせない重要な栄養素ですが、摂りすぎや偏りには注意が必要です。
例えば、以下のような、たんぱく質ばかりがメインになってしまっているケースです。
- ステーキ + ゆで卵
- 鶏むね肉 + プロテインドリンク
- サラダチキン + 豆腐
これらの組み合わせでは、たんぱく質への偏りが大きく、ビタミンや食物繊維、炭水化物などが不足しがちになります。
例③:野菜が一切ない

3つ目は、野菜がまったく含まれていない食事です。
これは、思い当たる人も多いのではないでしょうか。忙しかったり、外食が続いたりすると、つい野菜を摂るのを忘れてしまいがちです。
例えば、以下のような食事。
- 牛丼だけ
- ハンバーガー + ポテト
- カレーライス(具がほとんど肉とルーだけ)
こういった食事は、炭水化物とたんぱく質が中心になっていて、野菜がほとんど摂れていません。ちなみに、ポテトは野菜のように見えますが、実は「芋類」であり、野菜の代わりにはなりません。
このように、野菜が不足した食事が続くと、ビタミン・ミネラル・食物繊維などが不足しやすくなります。
例④:野菜や果物のみ

4つ目は、野菜や果物だけに偏った食事です。
一見ヘルシーで身体に良さそうに感じますが、実は栄養バランスの面では偏りがあります。
例えば、以下のような食事。
- サラダだけ
- スムージーのみ
- フルーツ盛り合わせだけ
このように、野菜や果物だけを食事として済ませてしまうケース。ビタミンやミネラル、食物繊維はしっかり摂れますが、たんぱく質や脂質、炭水化物が不足しがちになります。
健康を意識している人ほど、実はこうした偏った食事になってしまっていることがあるので注意が必要です。
例⑤:アルコール・ジュース・菓子だけ

5つ目は、アルコールやジュース、菓子だけに偏った食事です。
例えば、以下のようなものだけで済ます場合です。
- ビール・缶チューハイ
- 甘いジュース・清涼飲料水
- スナック菓子・チョコレート
これらを食事の代わりにしてしまうと、カロリーは摂れても、たんぱく質やビタミン、ミネラル、食物繊維などの必要な栄養素がほとんど摂れません。
栄養バランスは非常に悪く、健康に悪影響を及ぼすリスクが高まります。
バランスの悪い食事が続くとどうなる?

では、栄養バランスの偏った食事には、どのようなリスクがあるのでしょうか?
しかし、このような食事が習慣化してしまうと、少しずつ体に不調が現れ、やがては生活習慣病などのリスクが高まる可能性があります。
ここからは、具体的に偏った食事が、どんな影響を及ぼすのかを見ていきましょう。
炭水化物に偏った食事が体に与える影響
炭水化物に偏った食生活が続くと、体にはさまざまな悪影響が生じる可能性があります。
たとえば、以下のような影響が考えられます。
- 筋肉量の低下
- 免疫力の低下
- 疲れやすくなる
- 肌トラブルが起きやすくなる
- 肥満や糖尿病など、生活習慣病のリスクが高まる
主な理由は、たんぱく質・脂質・ビタミン・ミネラルといった栄養素が不足しやすくなるためです。
さらに、白米・パン・麺類などの精製された炭水化物ばかりを摂取していると、血糖値が急上昇しやすくなります。血糖値の急上昇は、肥満や糖尿病などの生活習慣病につながるリスクが高くなります。
炭水化物は大切なエネルギー源ですが、他の栄養素とバランスよく摂ることが大切です。
たんぱく質に偏った食事が体に与える影響
たんぱく質に偏った食生活が続くと、体には次のような影響が出ることがあります。
- ビタミンやミネラルの不足
- 臓器への負担
- 腸内環境の乱れ
たんぱく質に偏った食事では、炭水化物からのエネルギー供給が不足するため、体はたんぱく質をエネルギー源として利用しようとします。
しかし、たんぱく質は炭水化物に比べてエネルギー効率が良くありません。たんぱく質が分解されると老廃物が発生し、これが肝臓や腎臓に負担をかけることがあります。
また、消化しきれなかったたんぱく質が大腸まで届くと、悪玉菌のエサとなり、腸内環境が乱れる原因にもなります。
たんぱく質は筋肉や細胞の材料として欠かせませんが、過剰に摂りすぎず、他の栄養素とバランスよく摂ることが大切です。
野菜が一切ない食事が体に与える影響
野菜がまったく含まれていない食生活が続くと、体には次のような影響が現れることがあります。
- ビタミンやミネラルの不足
- 食物繊維の不足による腸内環境の悪化
- 便秘や消化不良のリスク増加
- 免疫力の低下や肌トラブル
野菜には、体の調子を整えるために欠かせないビタミンやミネラル、そして腸内環境を整える食物繊維が豊富に含まれています。これらが不足すると、体内の代謝がうまく進まなかったり、腸の働きが弱まったりしてしまいます。
特に食物繊維が不足すると、便秘になりやすくなり、腸内の悪玉菌が増えやすい環境ができてしまいます。これが続くと、免疫力の低下や肌のトラブルなど、全身の健康にも影響が及ぶ可能性があります。
野菜は健康を支える重要な役割を果たしているため、毎日の食事にしっかりと取り入れることが大切です。
野菜や果物のみが体に与える影響
野菜や果物だけを中心にした食生活が続くと、次のような影響が出ることがあります。
- エネルギー不足による疲れやすさ
- たんぱく質や脂質の不足
- 筋肉量の低下や体力の低下
- ホルモンバランスの乱れ
野菜や果物はビタミンやミネラル、食物繊維が豊富で健康に欠かせませんが、エネルギー量が不足しやすいため、疲れやすくなることがあります。
また、たんぱく質や脂質が十分に摂れないと、筋肉や体の修復、ホルモンの調整がうまくいかなくなり、健康維持が難しくなることもあります。
そのため、野菜や果物は積極的に摂りつつ、たんぱく質や脂質、炭水化物とバランスよく組み合わせることが大切です。
アルコール・ジュース・菓子類だけの食事が体に与える影響
アルコールやジュース、菓子類ばかりの食生活が続くと、以下のような影響が考えられます。
- 栄養素の極端な不足(たんぱく質、ビタミン、ミネラルなど)
- 血糖値の乱高下による疲労感やイライラ
- 肝臓への負担増加
- 免疫力の低下や体調不良
- 体脂肪の蓄積や肥満のリスク増加
アルコールや甘いジュース、菓子類は高カロリーでありながら、ビタミンやミネラル、たんぱく質などの必要な栄養素がほとんど含まれていません。そのため、これらばかり摂ると栄養バランスが大きく崩れてしまいます。
特にアルコールは肝臓で分解される際に負担がかかり、長期的には肝機能の低下や生活習慣病のリスクが高まる恐れがあります。
また、ジュースや菓子類に含まれる糖分は血糖値を急激に上げたり下げたりしやすく、体のだるさや集中力の低下、気分の不安定を招くことがあります。
健康を維持するためには、アルコールやジュース、菓子類は適量を守ることが大切です。
家族の栄養バランスが心配な方へ
おいしさで人気のオイシックスなら
買い出しなしで健康的な夕食に!

\ 初めての方限定!税込2980円! /
※定期購入ではなく、1回限りのセット
バランスの良い食事とは?

では、バランスの良い食事とはどのような食事でしょうか?
具体的には、以下のような食品がそれぞれに該当します。
- 主食:ご飯、パン、麺など(エネルギー源)
- 主菜:肉、魚、卵、大豆製品など(たんぱく質源)
- 副菜:野菜、いも類、海藻、きのこなど(ビタミン・ミネラル・食物繊維)
これらの食品を一つに偏ることなく、バランスよく組み合わせて、適切な量を摂ることが大切です。
毎食この3つがそろうように意識し、さまざまな食材を取り入れることが、健康的でバランスの良い食事につながります。
バランスの良い食事について詳しく
バランスの良い食事をするコツ

毎日の食事でバランスを整えるのは難しそうに思えるかもしれませんが、いくつかのポイントを意識するだけで、自然とバランスの良い食事に近づけることができます。
以下のコツを参考に、無理なく実践していきましょう。
- 「主食・主菜・副菜」への意識
- 食材の「色と種類」を増やす
- 「生野菜は両手いっぱい、加熱野菜は片手いっぱい」を目安に
- 加工食品や外食に偏りすぎない
- 1日単位、1週間単位でバランスをとる
「主食・主菜・副菜」への意識
バランスの良い食事の基本は、「主食・主菜・副菜」がそろっているかを意識することです。
最初から完璧を目指す必要はなく、「足りない要素があるかな?」と考えるだけでも、OKです。
例①:チャーハン
- 主食:〇(ごはん)
- 主菜:〇(卵や肉など)
- 副菜:△(野菜は少なめ)
野菜が不足しがちなので、サラダやスープを追加するのがおすすめです。
例②:ラーメン
- 主食:〇(麺)
- 主菜:△(チャーシュー1枚など)
- 副菜:△(少量のもやしやネギ)
主菜・副菜ともに不足気味。サラダやゆで卵を追加すると、栄養バランスがよくなります。
例③:おにぎり2個(梅・昆布)
- 主食:〇(ごはん)
- 主菜:×(たんぱく質がほぼない)
- 副菜:△(昆布や梅など少量)
たんぱく質・副菜が不足しています。具材を鮭やツナにする、ゆで卵やサラダを添えるなどの工夫が効果的です。
このように、「主食・主菜・副菜」のバランスを確認するだけでも、食事への意識が変わってきます。完璧でなくてもOKです。
 管理栄養士 こま
管理栄養士 こままずは“気づくこと”から始めて、できる範囲で改善していきましょう。
食材の「色と種類」を増やす
食事のバランスを整えるうえで、「食材の色」と「種類」を意識することはとても効果的です。色とりどりの食材を使うことで、栄養の偏りを防ぎやすくなります。
色を意識する
野菜や食材には、白・緑・赤・黄色・茶色など、さまざまな色があります。
色の異なる食材は、含まれている栄養素の種類も異なるため、できるだけ多くの色を取り入れることが、自然と栄養バランスを整えることにつながります。
<例>
- 緑:小松菜・ブロッコリー・ピーマン
- 赤:トマト・にんじん・パプリカ
- 黄:かぼちゃ・黄パプリカ・とうもろこし
- 白:大根・もやし・豆腐
- 茶:きのこ・ごぼう・玄米
種類を増やす
1回の食事で5〜10種類の食材を使うことを目安にすると、自然と栄養素の種類も豊富になります。
特別な料理でなくても、みそ汁に野菜を何種類か入れる、炒め物にキノコを足すなど、ちょっとした工夫で実現できます。



色と種類を意識することで、料理も見た目が鮮やかになり、食欲もアップします。
「生野菜は両手いっぱい、加熱野菜は片手いっぱい」を目安に
野菜をしっかり摂るために、「どれくらい食べればいいのか?」と迷うことはありませんか?
野菜は1日あたり350gの摂取が目標とされていますが、毎回グラムを量るのは大変です。
そこで役立つのがこの「手ばかり法」。
生野菜はかさが多いため、両手に乗るくらいが1食分の目安。
加熱した野菜はかさが減るので、片手に乗るくらいがちょうどよい量になります。
毎食この「手のひら量」を意識するだけで、自然と1日の野菜摂取量に近づくことができます。



この方法は、管理栄養士が実際の栄養指導の現場でもよくお伝えする、わかりやすく実践しやすい目安です。
加工食品や外食に偏りすぎない
加工食品や外食は手軽で便利ですが、脂質や塩分が多く、栄養バランスが偏りやすいという特徴があります。
そのため、頼りすぎないことが健康的な食生活のポイントです。
どうしても利用する場合は、以下の点に注意して選びましょう。
主食(ご飯・パン・麺類)に偏らないようにする
→炭水化物ばかりのメニューに注意しましょう。
揚げ物ばかりにならないようにする
→焼く・蒸す・煮るなど、脂質の少ない調理法を選ぶと◎。
サラダや小鉢などの副菜をプラスする
→不足しがちなビタミン・ミネラル・食物繊維を補えます。
ソースやしょうゆなどの「かけすぎ」に注意する
→塩分のとりすぎを防ぐために、つける程度でOK。
デザートは控えめに。選ぶなら果物入りのものを
→甘いものが欲しいときは、フルーツ入りや小さめサイズに。
「完全に避ける」のではなく、「どう選ぶか・どう組み合わせるか」が大切です。



加工食品や外食も、ちょっとした工夫でバランスよく楽しめます。
1日単位、1週間単位でバランスをとる
食事のバランスは、1食ごとに完璧を目指す必要はありません。
大切なのは、「1日単位」や「1週間単位」で、トータルのバランスを意識することです。
実際、管理栄養士であっても、毎食すべてを完璧に献立を立てるのは簡単ではありません。だからこそ、長い目で見て調整することが大切です。
たとえば、朝食が偏ってしまっても、昼食や夕食で不足を補うようにすればOKです。気楽に、でも少しずつ意識しましょう。
無理なく続けられる「バランスのとり方」が、健康的な食生活への第一歩です。
よくある質問(Q&A)食事のバランス


加工食品を使っていると、やっぱりバランスの悪い食事になりますか?
一概にそうとは限りません。
加工食品の中には、冷凍野菜や魚の缶詰、レトルト味噌汁など、栄養価が高く便利なものもあります。大切なのは「何を選ぶか」と「どう組み合わせるか」。加工食品を使っていても、栄養バランスは十分に整えることができます。
食事の回数が少ないと、バランスの悪い食事になりますか?
食事回数の少なさだけで「バランスが悪い」とは言えません。
1日1〜2食でも、各食で栄養素がしっかりと摂れていれば、問題ないこともあります。ただし、エネルギー不足や栄養の偏りには注意が必要なので、少ない回数でも「主食・主菜・副菜」を意識した構成が大切です。また、もちろん1日3食が望ましいです。
忙しくて野菜が取れない日があるのですが、それもバランスが悪いですか?
1日単位で栄養が偏っても、すぐに体に悪影響が出るわけではありません。
もちろん、毎食バランスの良い食事をとるのが理想ですが、忙しい日が続くと、なかなか難しいこともありますよね。実際に管理栄養士が献立を立てる際も、「1週間」や「1カ月」といった長いスパンで全体のバランスを考えることが多いです。難しいときは、日々の食事にこだわりすぎず、長期的に見て栄養バランスを見直していきましょう。
コンビニごはんばかりだと、バランスの悪い食事になりがちですか?
選び方次第で、コンビニ食でも栄養バランスは整えられます。
例えば、おにぎり+サラダチキン+野菜スープなどを組み合わせれば、主食・主菜・副菜が揃います。栄養成分表示をチェックして、たんぱく質・食物繊維を意識すると◎。
野菜や果物ばかり食べているのに、バランスが悪いって本当ですか?
はい、野菜や果物だけでは、たんぱく質や脂質、ミネラル類が不足しやすくなります。
「ヘルシー=バランスが良い」とは限らず、“全体の栄養バランス”が整っているかが大切です。豆腐や卵、魚なども意識して取り入れましょう。
簡単にバランスの良い食事を摂る方法はありますか?
ミールキットの活用がおすすめです。
ミールキットは、あらかじめ食材と調味料がセットになっていて、栄養バランスも考えられているものが多く、手軽に主食・主菜・副菜をそろえられます。
調理も短時間で済むので、忙しい方や料理が苦手な方でも無理なく続けられます。
詳しくは「オイシックスCookBox」の記事をご覧ください。
まとめ:バランスの悪い食事は、早めに見直そう


この記事では、バランスの悪い食事の具体例や、身体への影響について解説しました。
要点をまとめると以下の通り。
- 炭水化物・たんぱく質・野菜のいずれかに偏った食事は、栄養バランスが崩れやすい
- 偏った食事が続くと、生活習慣病など健康リスクが高まる可能性がある
- バランスの良い食事は「主食・主菜・副菜」がそろっていることが基本
バランスの悪い食事は、今すぐに体に影響が出るわけではありませんが、将来的な健康リスクを高めてしまう可能性があります。
「最近、ちょっと偏ってるかも…」と感じたら、ぜひ次の食事から少しずつ見直してみましょう。
また、「バランスよく食べたいけど、よく分からない」「毎日考えるのが面倒…」という方には、ミールキットの活用もおすすめです。あらかじめ栄養バランスが考えられており、簡単に調理できるので、忙しい人でも続けやすい方法のひとつです。
今なら人気のOisixCookBoxが税込2980円でお得に試せるチャンスです!


\ 初めての方限定!1食298円! /
※定期購入ではなく、1回限りのセット



気になる方は、ぜひお試しから始めてみてください。